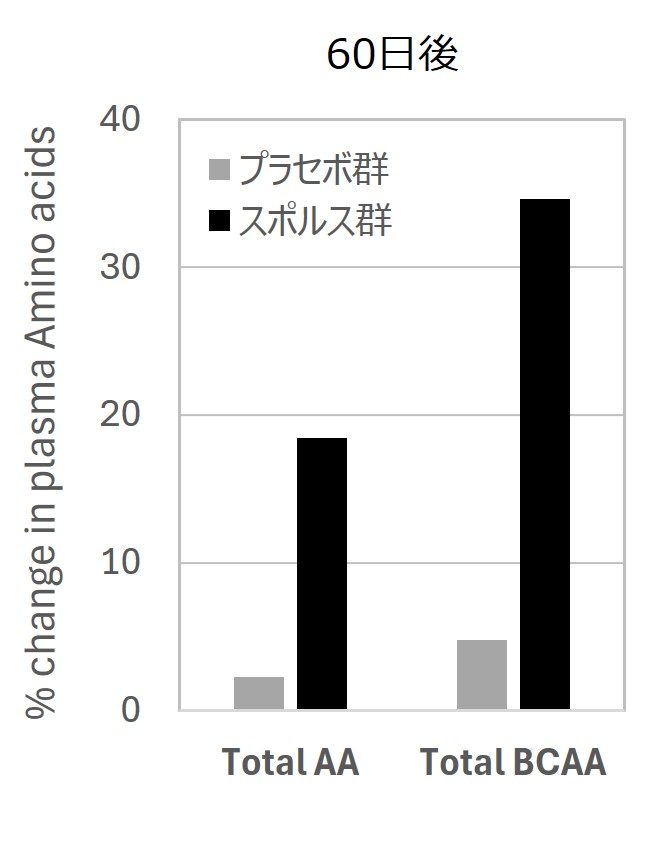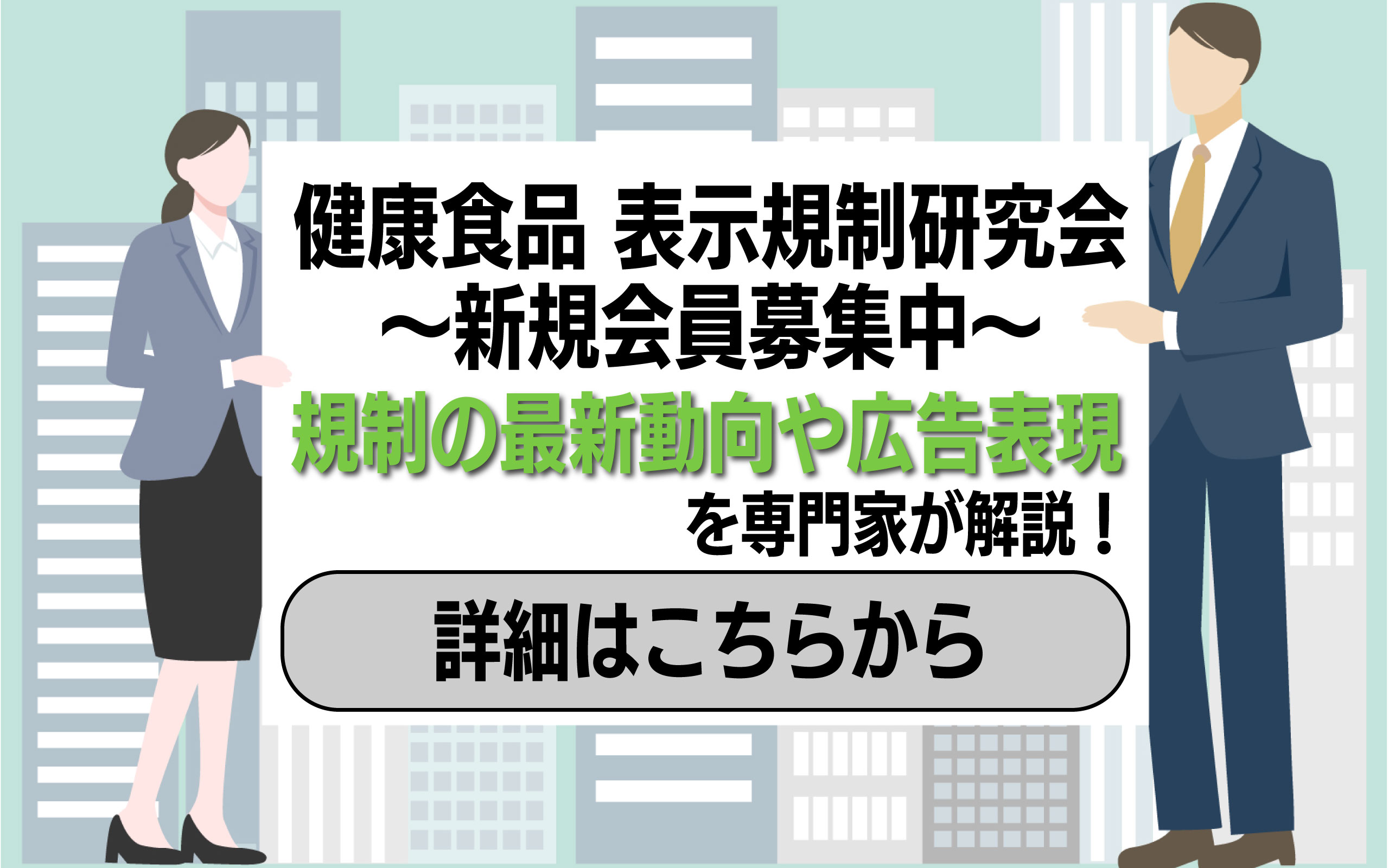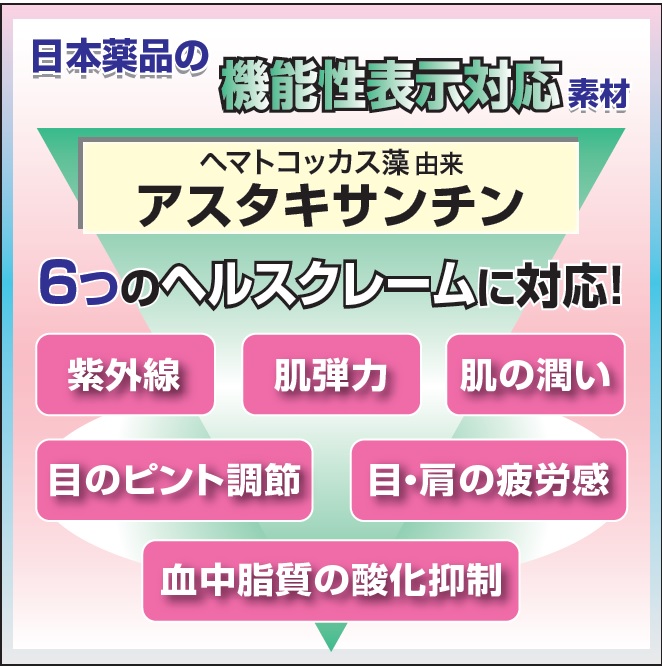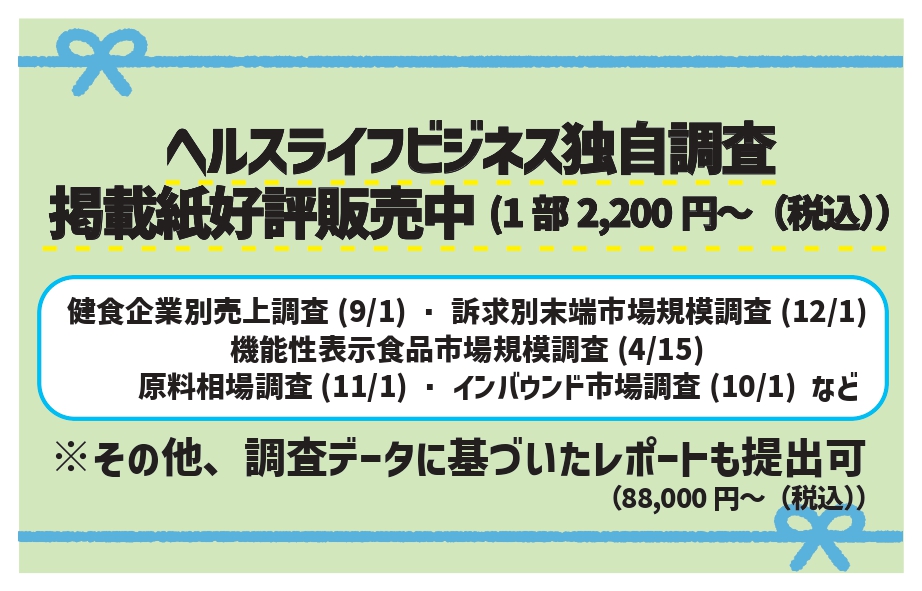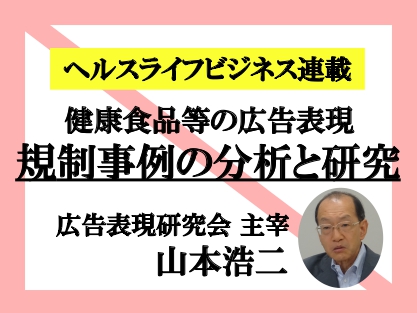病気になったら薬で治せばいい(110)
バックナンバーはこちら
この日の作業が終わると、上田さんは一冊の本を見せてくれた。
「戦友たちと出したんだ」と照れたような顔をする。本のタイトルには、「ラバウル~最悪に処して最善を尽くす」とある。出したのはラバウル経友会となっている。
「ラバウルにいたときの経理部の仲間だよ」
正確には第8方面軍経理部だそうで、表紙をめくると、森田経理部長以下20名の写真があった。1942年(昭和17年)11月に今井大将指揮下の陸軍第8方面軍はオーストラリアの統治下のパパウニューギニアのラバウルに上陸した。近くのガダルカナル島では日米両軍が死闘を繰り広げており、地獄絵図の様相を呈していた。
「大変だったでしょうね」というと、「そうでもなかったんだ」という。なぜかというと、ラバウルではいち早く補給が断たれることを予想し手を打っていた。まずは食糧大増産計画である。生産のために畑の開墾に今村司令官が自ら畑を耕したという。タピオカ(キャッサバ)などのほかサツマイモや陸稲など生産を行い、十分な食料を手にした。
上田さんもそろばんを放り出して、食糧増産や確保に走り回った。さらに地下を要塞化して、敵の来襲に備えた。だから敵機が来襲しないときのラバウルは戦時下と思えないほど平穏だったという。このため軍の士気は高く、住民の信頼も得ていた。だから米軍は爆撃に来ることはあっても、上陸して来ようとはしなかった。戦争が終わると、ほとんどの兵隊が生きて本土に帰ることが出来た。
「今村という大将が偉かった」
その日は上田さんが気に入っている高田馬場のイタリアンレストランでご馳走になった。ワインを飲みながら話は先ほどの続きになった。
「私の父もラバウルにいたことがあるんです」というと、「そうかァ」と顔を上げた。私の父は日本電気に勤める技術屋だった。そのためか、召集されると陸軍で飛行を操縦することになった。爆撃機で中国から南方を転戦して、最後は満州で終戦を迎えている。2度程墜落して、このときの傷が手に残っていたのを覚えている。ともあれ戦争のことをあまり語りたがらなかった父が、ラバウルの印象は良かったのか、酔うとよく「ラバウル小唄」を歌った。
ただしそこでマラリアに罹った。そのせいで晩年まで、身体が弱るとその症状が出た。震える身体を布団に包んで抑えながら、母が「お父さんの戦争は死んで終わるのよ」といった言葉を思い出す。
帰りの西武線の電車に揺られながら、上田さんの今日の話を思い出していた。なるほど健康食品問題の解決は食品と医薬品のダブルゾーンに線引きすることには違いない。しかし厚生省の薬務局にいくら要望しても、薬の側からの線引きになってしまう。
だから上田さんは「もっと大所高所に立って考えないといけない」という。足元を見ていては、自分たちの利害ばかりになってしまう。だから厚生省の薬務局は大所高所に立つべきだというのだ。ここでいう大所高所とは国民の健康だそうだ。しかし彼らも当然国民の健康の時代からずっとそうして来た。これが彼らの考える国民を健康にすることである。だから食品はいらないのだ。だから要望書は“ゼロ回答”だったのだ。
これでは食効など永遠に認められそうにない。なんだかお先真っ暗だと思った。ところがこの時期すでに水面下で動きが始まろうとしていた。
(ヘルスライフビジネス2018年11月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)