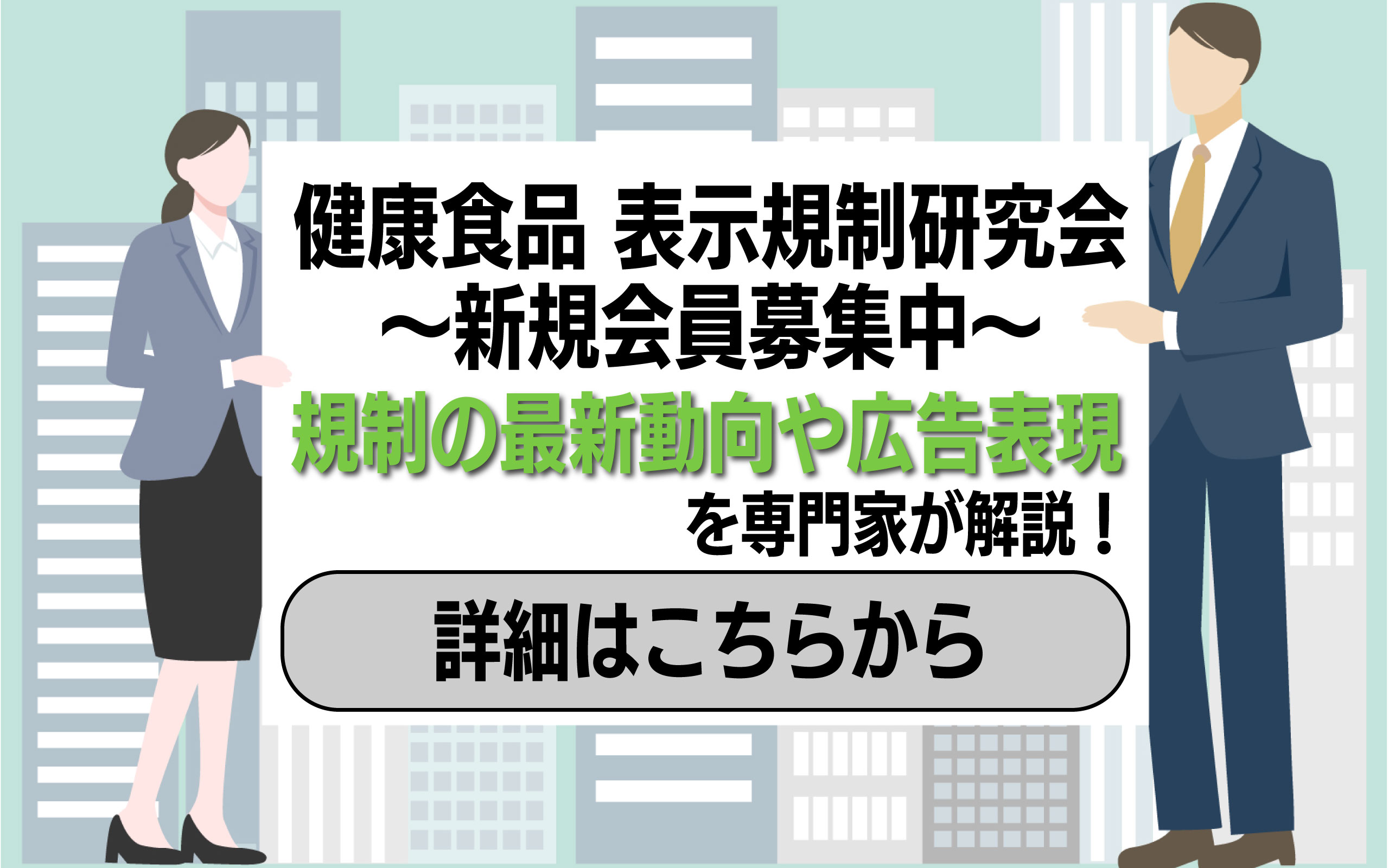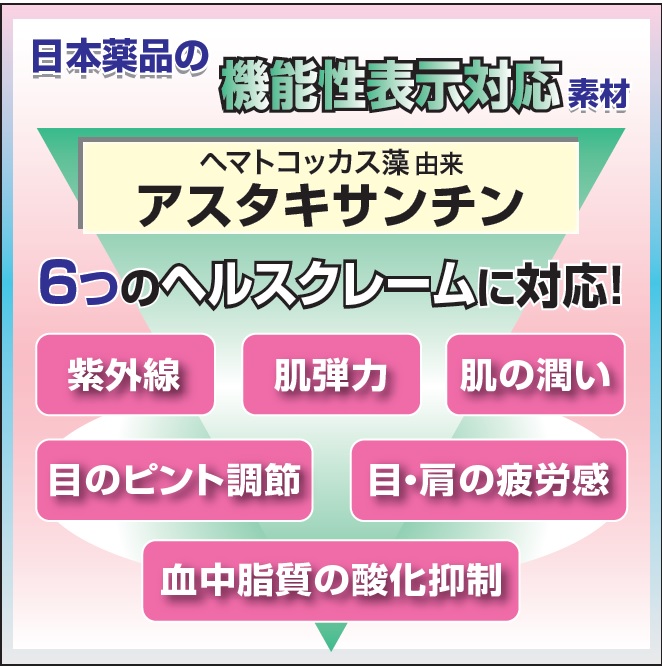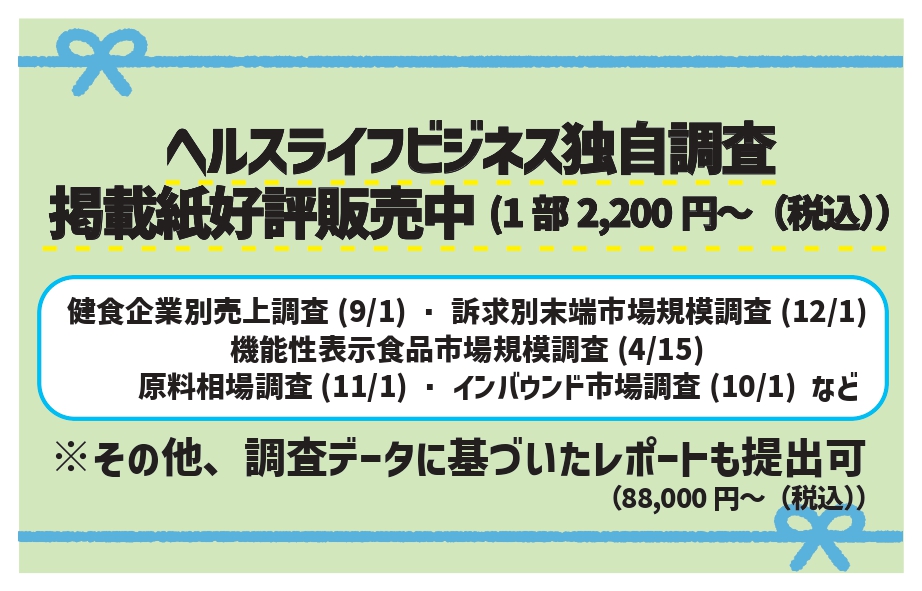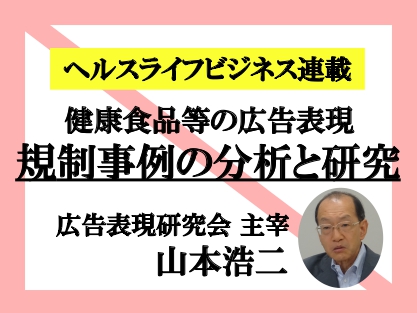「もう行くのやめました」で一件は落着した(124)
バックナンバーはこちら
その日、平野さんは片付ける仕事があり、人の出払った事務所で一人お弁当を開いた。しばらくして気付いた。静まり返った社内に人の話声がする。聞き耳を立てると、それは会議室の方からだということが分かった。それも園田社長と編集長の声だった。慣れてくると会話の中身が次第に分かるようになった。
「葛西博士の傷のことだったのよ」と平野さん。壁に耳あり、障子に目ありである。「それがねえ…」と平野さんは辺りを伺うようにして話す。私たちは思わずにじり寄った。
一月前のことだ。その日、園田社長は神田の駅近くの居酒屋で仕事関係の人と飲んでいた。飲み終わると別れを告げ、駅に向かおうと飲み屋街を歩いていた。その時、道の逆側の歩道に面したスナックのドアが開いて、酔っぱらった葛西博士が出てきた。次の瞬間、見送りに出てきた女の人と軽くチュウをしたのだそうだ。とっさに園田さんは路地に身を隠したという。
ため息交じりに「えらい物を見ちゃった」という。「それでどうしたんですか」編集長も興味津々である。物陰からそっと覗くと、もう彼らの影も形もなかったそうだ。
「夢でも見たんじゃあないですか」と編集長。しかし園田さんは「確かに夢であればいいと今でも思っているよ」という。しかし顔は間違いない。白い半そでのワイシャツ、グレーのズボン、それにカバンだっていつも見ているのと同じだった。「彼に間違いない」という。
「しかしよくそんなお金がありましたね」と編集長。博士は給料袋を封も切らずに奥さんに渡しているはずだった。そしてわずかな小遣いをもらう。だから本を買うにも昼飯を切り詰めている始末だ。そんな男が、場末とは言え“お姉ちゃん”のいるスナックで豪遊できるわけがない。結論が出ないまま話は終わった。
それを聞くと、「ほら見なさい。図星でしょう」と宇賀神さんは勝ち誇ったようにいった。だからと言ってそのスナックの女が引っ掻き傷の原因と決まったわけではない。まだ点と線がつながらない。
「確かに、博士はいつもお金がないから、そんなところに行けるわけはないわね」と平野さん。「ましてやお金のない男なんて、水商売の女が相手にするわけないわ」と宇賀神さん。女はお金よ、ときついことをいう。博士は結婚しているからお金がない。しかし私は結婚してなくてもお金がない。「だっていっぱい飲んじゃうからでしょ」と平野さん。
とにかく博士にないはずのお金がある。「とすると、会社のお金ェ」。つまり着服したということか。金庫は平野さんがお尻の下に敷いているから手出し出来ない。後は広告と購読の集金のお金しかない。帳簿と売掛を洗ってみたが、問題はなさそうだったという。
飲み会から数日すると、岩澤君から報告があった。取材先の企業の担当者が行きつけの神田のスナックで葛西博士を見かけたという。彼には会ったことがあるので覚えていたが、博士の方では忘れているようだったという。だいぶ酔っていて、スナックの女の子と仲良くやっていたよということだった。「これが傷の原因でしょうね」と岩澤君。園田さんが見たことの裏付けにはなるが、これも傷には直接つながらない。
ところがようやく博士の傷が癒える頃になって理由が判明した。本人から編集長に話があったのだ。それによると、帰りにたまたま入ったスナックで、従業員の“お姉ちゃん”と仲良くなった。出身が同じ青森だったからだ。商売とは言え、女の子と親しくなるのは嫁さん以来だったようだ。それでつい入れ込んだ。何度か通ううちに、帰りに外でホッペにチュウをしてくれるようになった。単なるサービスである。ところがその時口紅がたまたまワイシャツの襟についていた。それを見とがめた奥さんと口論になり、例の傷になったのだ。
「もう店には行くの止めました」と葛西博士。これで一件落着したのだ。資金源は講演料と依頼原稿のお金だった。この頃、もらったお金の半分は会社に入れて、あとの半分は個人のものにして良いことになっていた。「やましいお金じゃァなかったんだ」と編集長。雨降って地固まるで、その年の秋に彼の奥さんのお腹に新たな命が宿った。
(ヘルスライフビジネス2019年6月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)