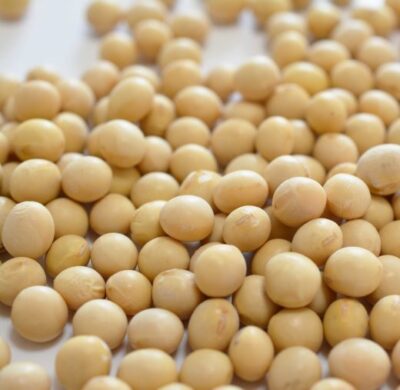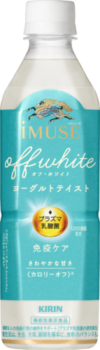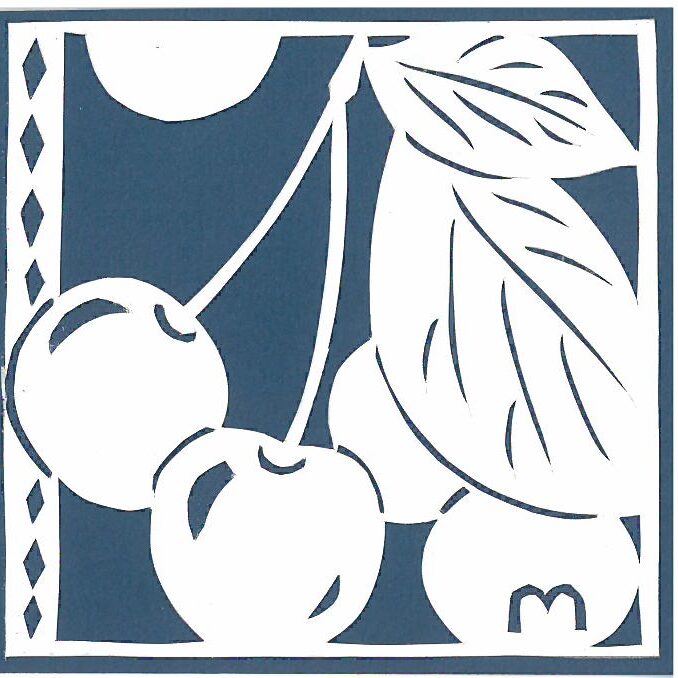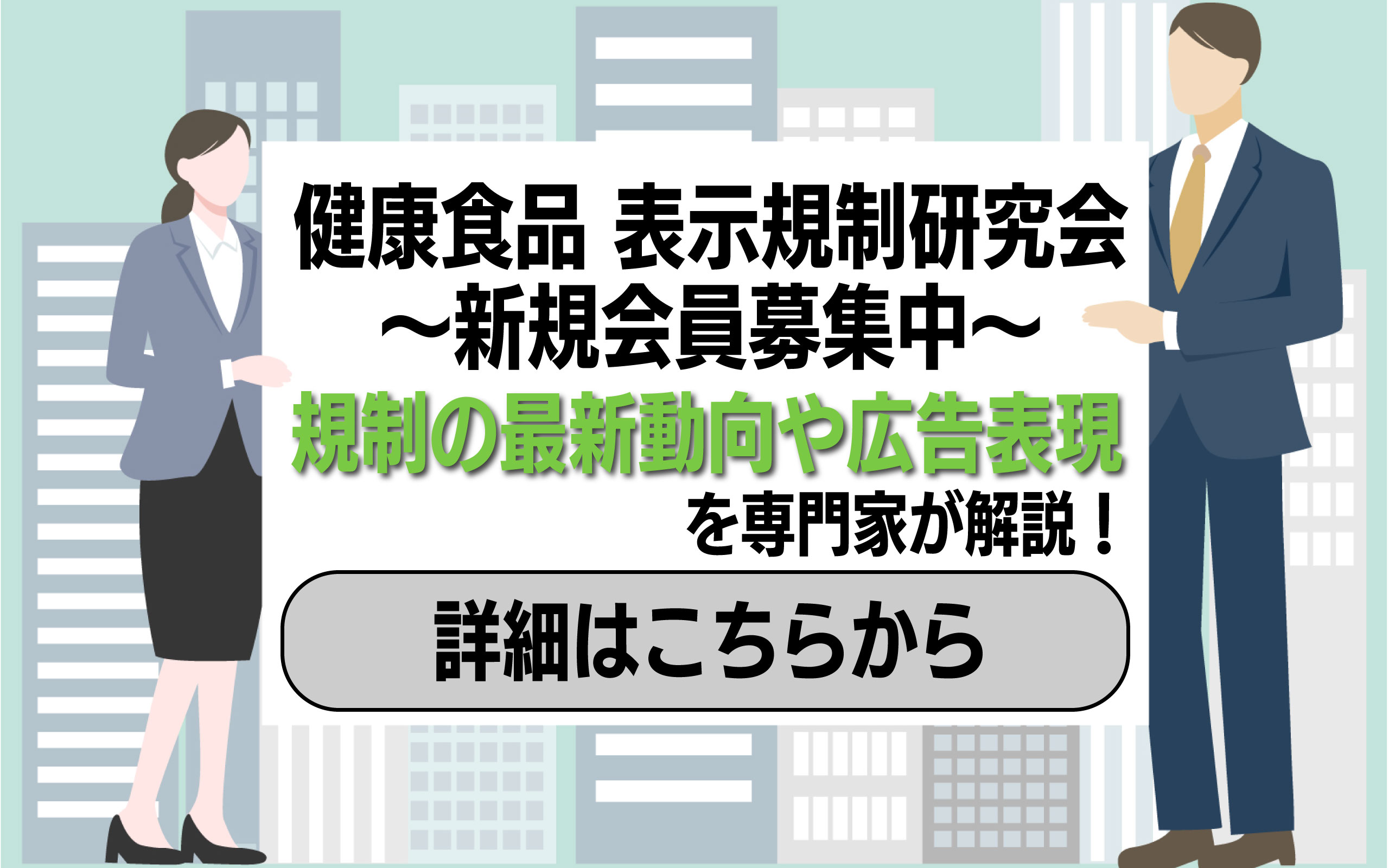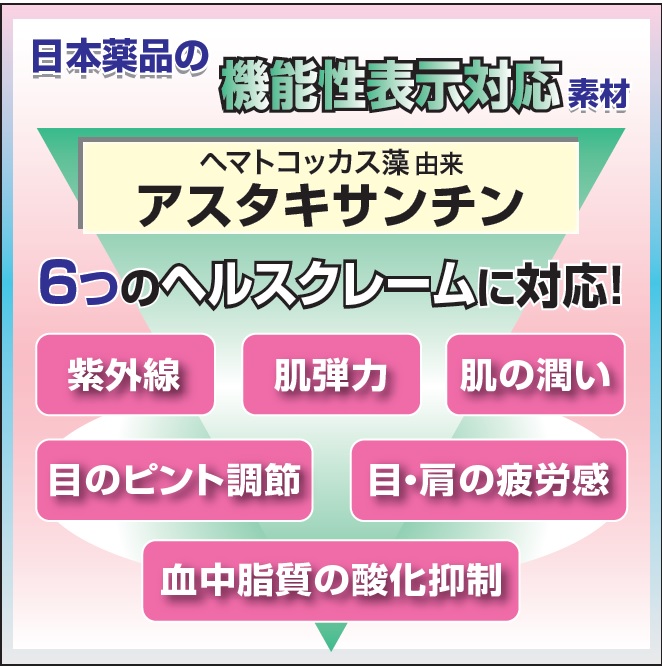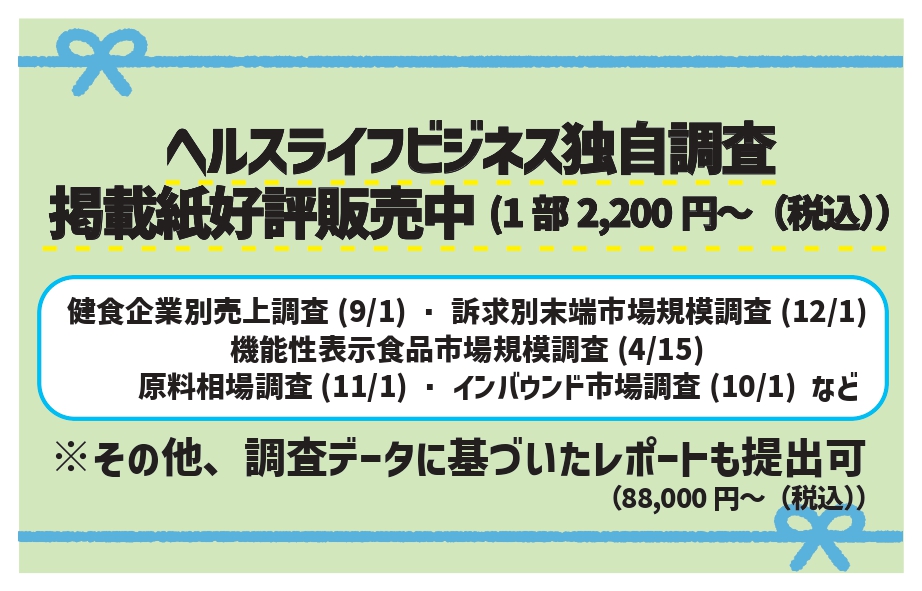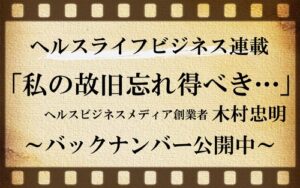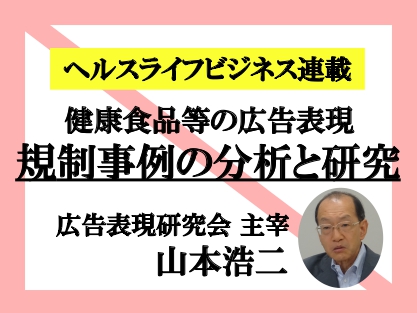ストレス時代の栄養は所要量では足りない(127)
バックナンバーはこちら
「『コ』の栄養学!?」と岩澤君は首を傾げる。まず「コ」という字が「個」であることを分かっていない。
「『コ』とは個人のことだ」というと、渡辺先生は説明し始めた。栄養学はそれまで集団を対象にした。ところが食生活や運動習慣など生活習慣が違う。それぞれの人に合った栄養学が必要な時代になっているんだという。そうでないと生活習慣病の増加を抑えることが出来ない。
「そのことを豊川さんは指摘しているんだ」
そういわれると、なるほどと思う。それまで毎年国民栄養調査の記事を書いて来たが、厚生省がくれる資料の中で、栄養素別の摂取量の分布なんて見たことがなかった。
「なぜ役所はこの資料を出さないんでしょうかねェ」というと、「おそらく都合が悪いからだろう」と渡辺先生はいう。
そこに葛西博士が帰ってきた。満面の笑みで、「豊川さん、OKですよ」と結果を伝えた。豊川・渡辺対談を紙面でやることを了解したというわけだ。
翌週、神田郵便局の隣のホテルで対談を行った。やってきた豊川という男は文書を読んだときのイメージとだいぶ違っていた。私の人生で会った東大医学部の教官の多くは、偉そうで嫌な奴が多かった。あからさまに上から目線で「なんだ健康食品の業界紙ごときが」といった態度をとる。もちろん、私が会った人たちがそうなのであって、全てでないとは思う。しかし豊川さんからもそうした匂いがプンプンしていた。
対談が始まると、渡辺先生とは個人に即した栄養学に立たなければいけないということでは一致した。豊川さんは『日本型食生活のすすめ』の本の中でも書いていた。
「顔が一人ひとり同じでないように、実は栄養素の所要量も一人ひとり異なっているものです」と。
しかしその栄養を確保する方法では渡辺先生と違っていた。食事が大事であるということは同じだったが、特に不足している栄養素やストレスで失われやすい栄養素はサプリメントで補うという考えを頑なに否定した。
栄養所要量の栄養素の摂取基準は平均値で、必ずしも個人の必要量を満たしているとは限らない。しかもこの基準を満たしているかどうかを調べた国民栄養調査でも栄養素の分布で見ると、平均値では摂れているものの、多過ぎる人や少ない人がかなりの数に上る。このことは豊川さんと渡辺先生も認識は一致する。ところがストレスによる栄養の体内要求量が上がることを豊川さんは受け入れることが出来なかった。
「それも仕方がないことかもしれないね」と渡辺先生は豊川さんと別れた後にいった。サプリメントを支える栄養学の背景にはストレス学的な健康管理という考え方がある。それからすると、栄養所要量は健康を維持するための栄養の量である。確かに大切ではあるが、ストレスに曝される現代人にとってそのストレスで失われる栄養素の増加を「保健量」というが、これを加味しないと生活習慣病から身体を守れない。
「所要量ではビタミンCは1日50㎎といわれているが、ポーリング博士は2000㎎必要だといっている」
ストレスがかかると体内で消費される栄養素で増えるものがある。分りやすいのは喫煙で体内の消費が増すとされるビタミンCだ。
「マグネシウムのことも田多井さんの本で学んだだろう」と渡辺先生から言われて思い出した。東京農業大学の教授だった田多井吉之介さんの本で『ストレスとは何か』という本だった。
(ヘルスライフビジネス2019年7月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)