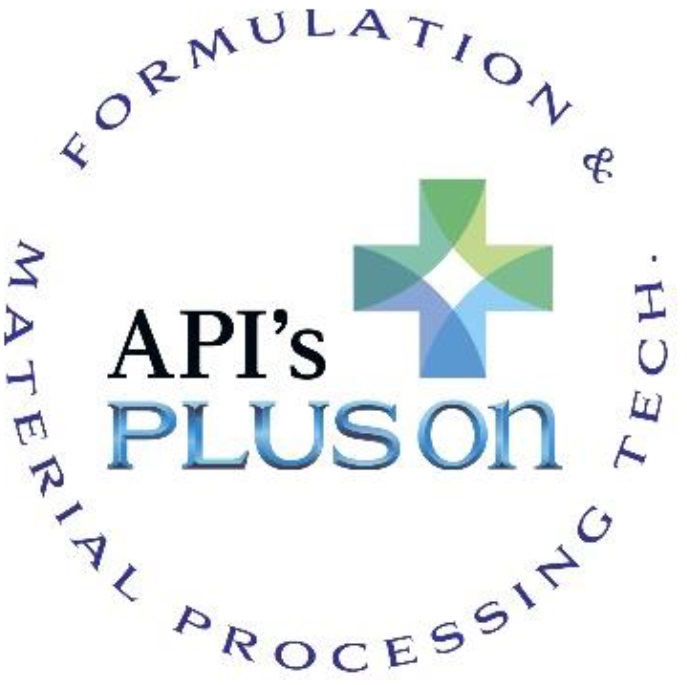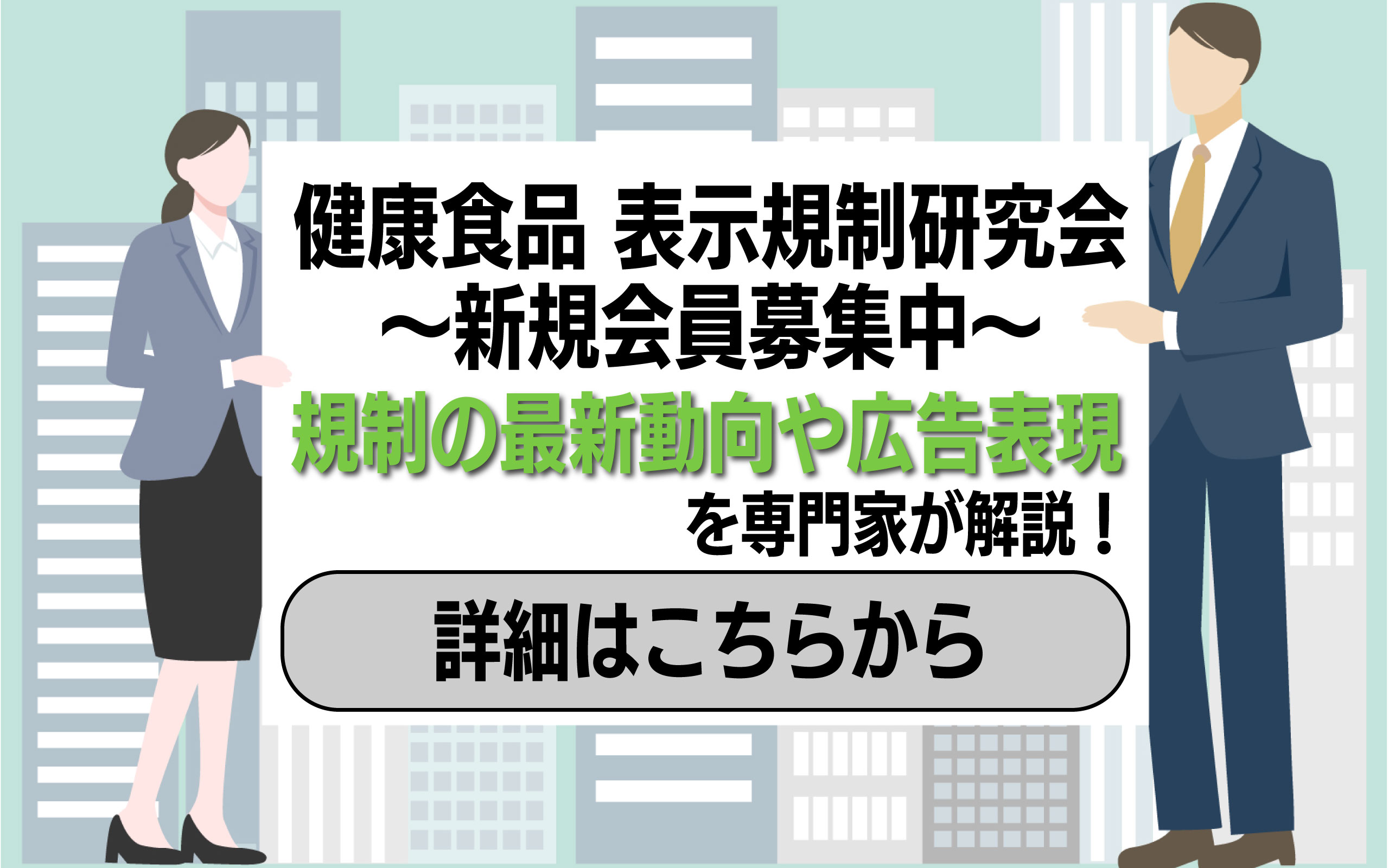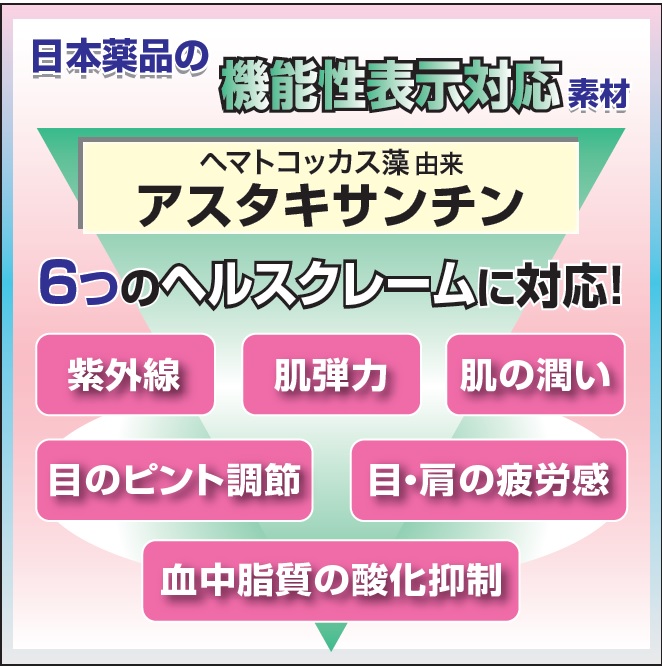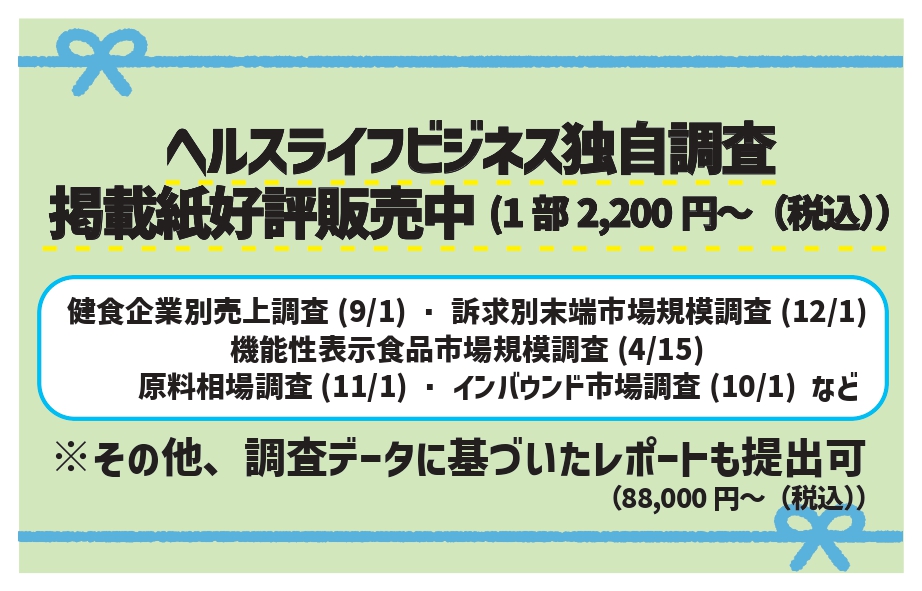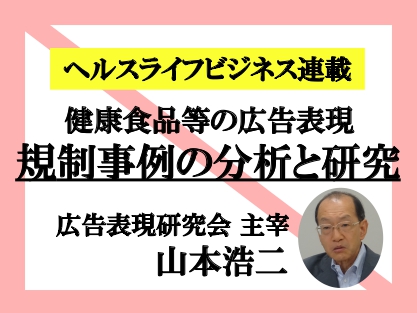締切迫り、苦肉の策で米国特集(56)
バックナンバーはこちら
米国から帰国して、いつもの生活に戻った。御茶ノ水の編集部では迫りくる締め切りに頭を抱えていた。編集部のほとんど、といっても3名だが、2週間も日本を空けていたので、その間に仕事が山積みになっていた。しかし、肝心の取材は何もしていなかった。それでも何か書かなければならない。
ところが4人目の編集部員である経理事務の宇賀神女史は協力する気がなさそうだ。彼女は消費者系の元新聞記者だった。しかも経理も出来るので、面接のときそれを付け加えた。口は禍の元である。記者として面接を受けたと思っていたのに、どうしたことか経理として採用された。世の中はえてしてそういうものだ。それで記者として応募したのに、「失礼しちゃうわ」とその話になると文句を言う。うるさいので仕方なしに経理事務兼記者ということにして、記事も書くようになった。
しかし、本人は記者だと思っているのに、今回自分だけ米国に行けなかった。その腹いせもあってか、「私は経理事務で記者ではない」と締め切りに協力しない。「ガア、ガア」とうるさい“アヒルのおばさん”だと言われていたが、編集と経理を自分の都合で使い分ける“コウモリおばさん”でもあることが判明した。
「そんなこといわずに手伝ってよ」、「いやです」、「前は書きたがっていたじゃないの」、「いやと言ったら、絶対に嫌です」
そんなときに限って印刷屋の進行係の市川さんから入稿予定を迫る電話が入る。
「遅れた物は、遅れて出す」これが市川さんの口癖である。原稿の入稿を遅らせた方が悪いんだから、印刷屋は発行日がずれても一向にかまわないということを言いたいらしい。それなら放って置けば良いものを、その割にはやたらに電話をかけてきて、この言葉を何度も繰り返す。結構なプレッシャーになる。あちらはあちらで、印刷のスケジュールが狂うので、予定日には刷り上げたいのだろう。零細新聞社と印刷屋の互いの事情で、新聞が発行日にとまでとは行かないが、発行日を1日、2日過ぎたあたりになんとか刷り上がる。
この日も2回目の催促の電話が来た。
「ああ、こちらは一向にかまわないんだ」といって市川さん、いつものセリフで「遅れたものは、遅れて出す」。
編集部で入稿の会議をしたが、国内を取材していないのでネタがない。つまり書くことがないのである。これではいつまでたっても原稿はできない。ということは入稿できないということになる。
「ええい!もう仕方がない。米国の記事で埋めちゃおう」ということになった。にわかに米国特集になった。それならば話は簡単だ。ネタは山ほどある。ということで、3名がそれぞれ手分けして記事にかかった。
そうして夏が過ぎ、お盆も過ぎた8月22日だった。台湾で航空機の墜落事故が起こったことをテレビのニュースが伝えた。というのもこの飛行機に、作家の向田邦子さんが乗り合わせていたからだ。彼女は前年には「あ・うん」がNHKで放送され評判になっていた。さらに直木賞も受賞した。作家として脂の乗り切った時期だっただけに、彼女の死は大きく報道された。
さて、4人目の編集部員である宇賀神女史はこの向田邦子さんの熱烈なファンだった。明治大学文学部を卒業していた文学少女の成れの果てで、小説も書いていた。読むように言われて、原稿を何度か渡された。向田邦子張りの小説だが、どうも違う。やはり業界紙の記者をしている方が向いているといって返したらむくれた。そのうち向田邦子さんお妹さんがやっていた赤坂の小料理にも通うようになった。宇賀神女史はやはりミーハーだった。妹さんと親しくなって赤坂が通いはしばらく続いたが、そのうち言わなくなった。小説のことも言わなくなったので自分の才能に気付いたのだろう。以降、相変わらず文句は言うが記事を書いている。
(ヘルスライフビジネス2016年8月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)