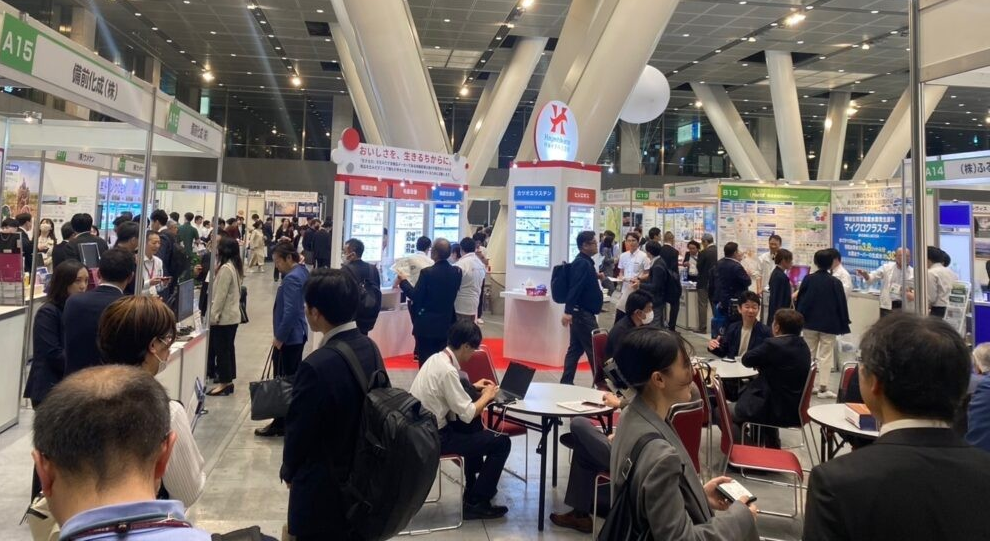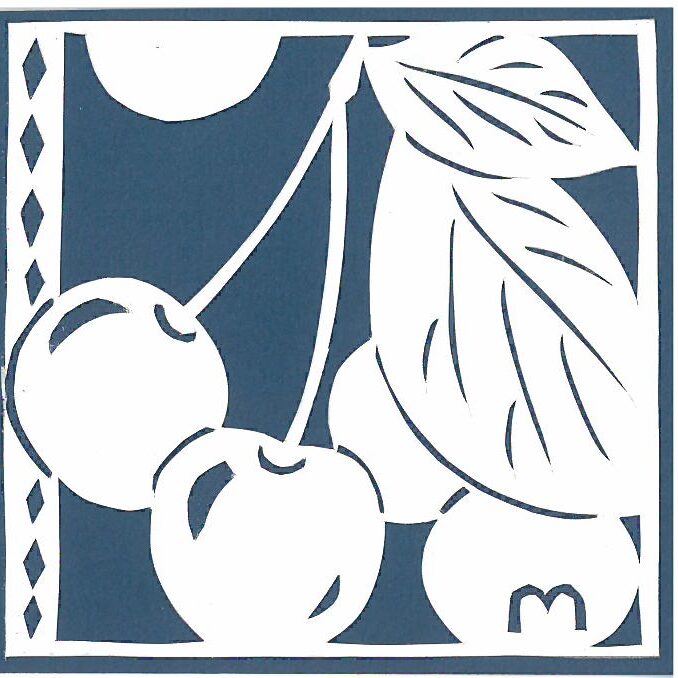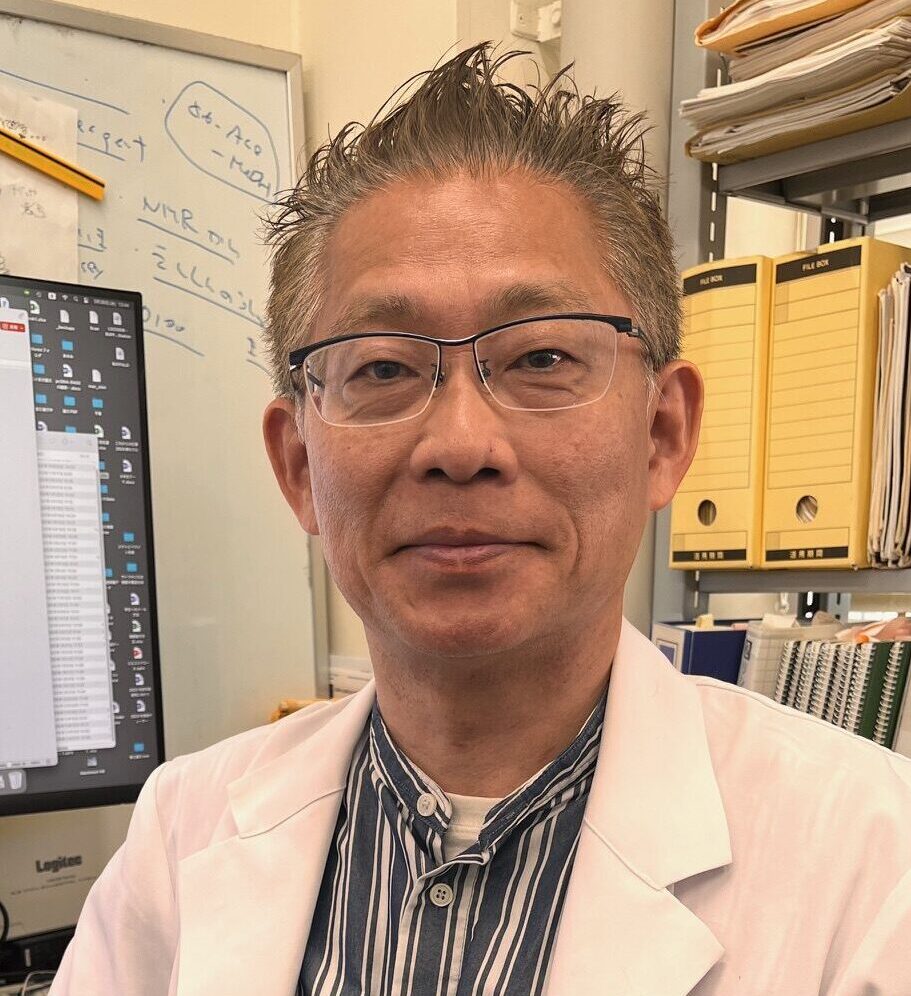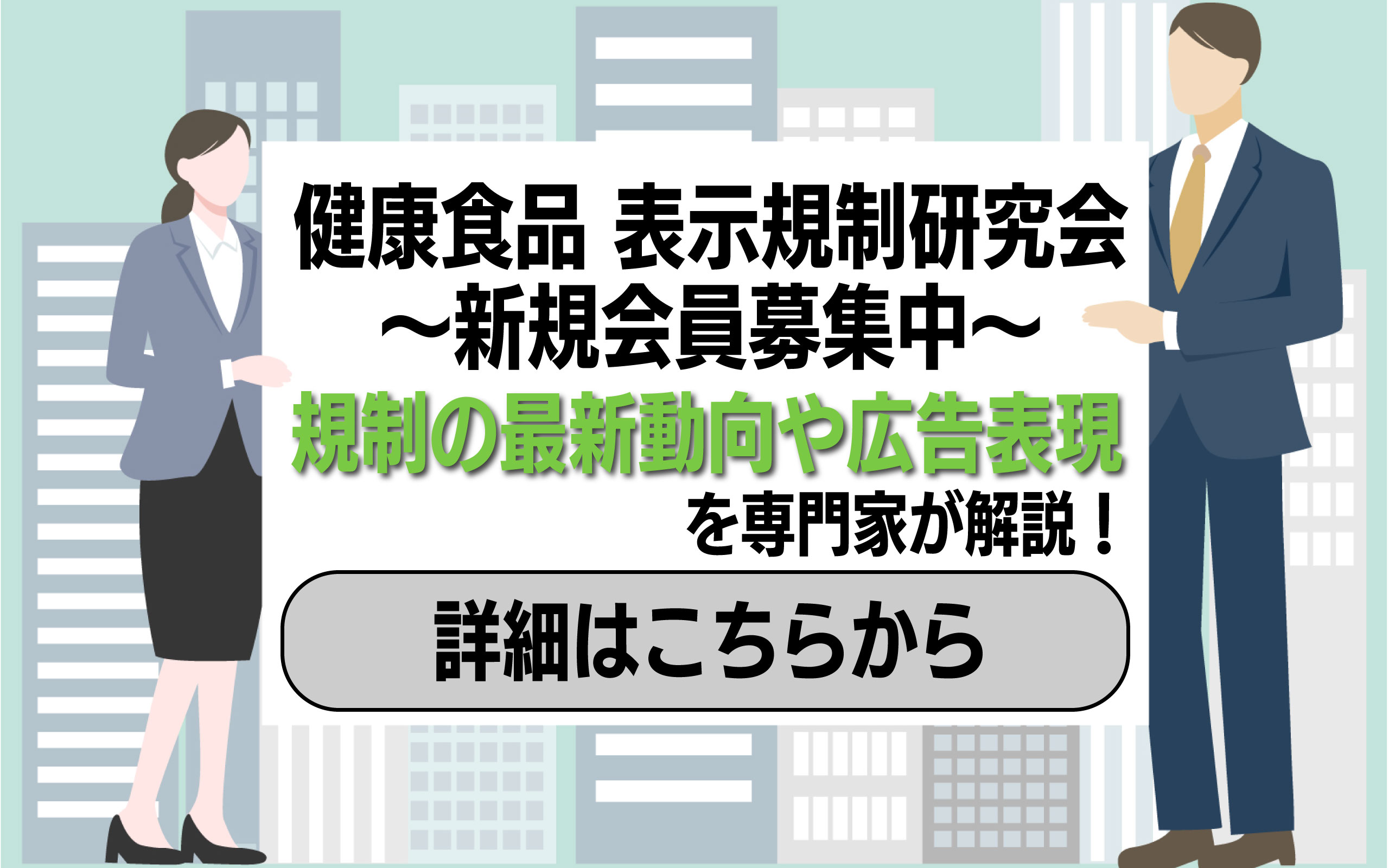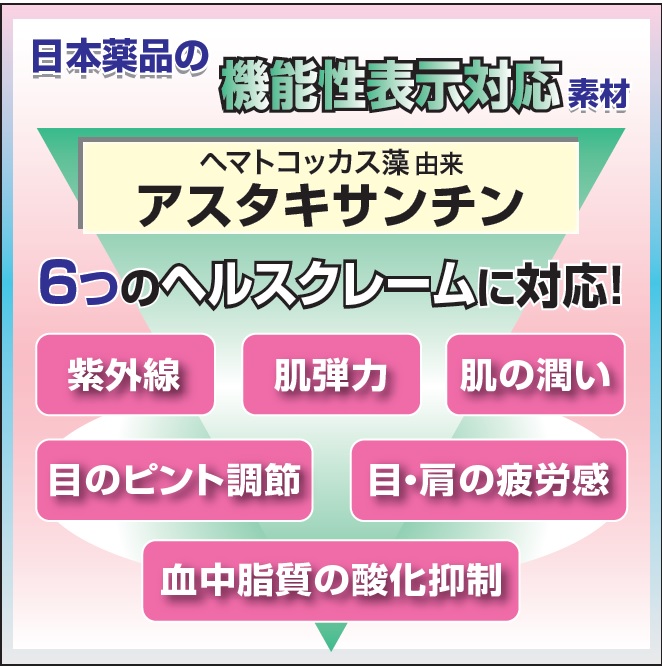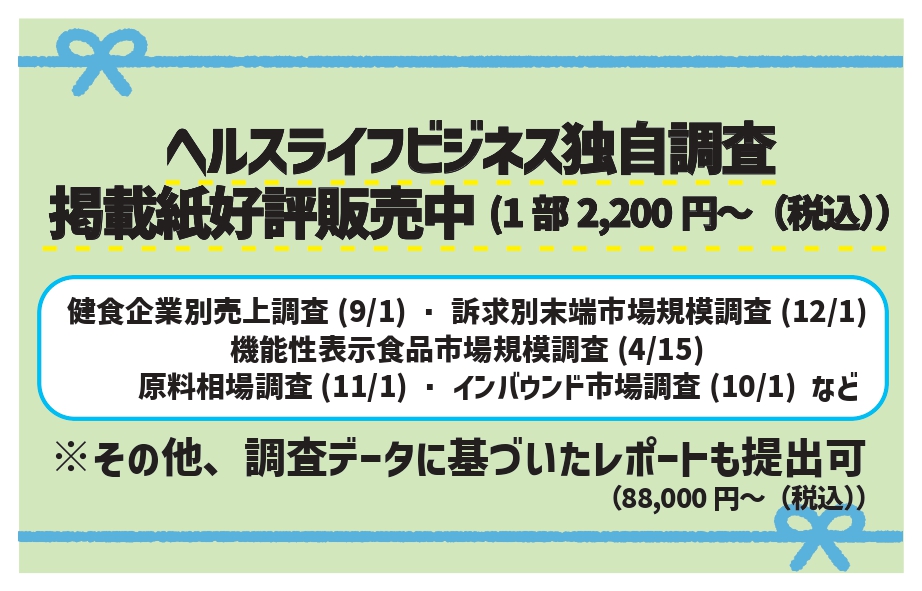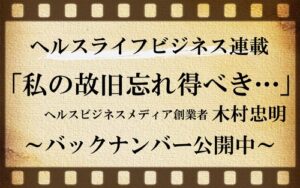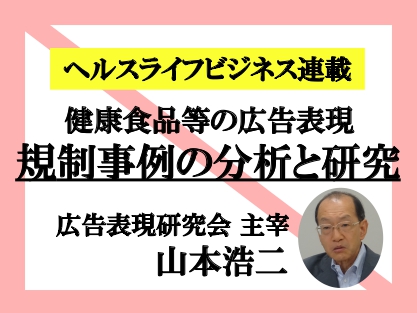栄養ドリンクを捨て置くわけにはいかない(94)
バックナンバーはこちら
お酒を口に運ぶと、加藤さんは続ける。
「翌年の昭和36年に改正薬事法は施行されたんだが、それから10年経った昭和46年に国46通知がでている」
この間に何があったのかというと、食品の健康化が始まっている。その一つが「オロナミンC」である。
ドリンク剤の市場は1950年代の半ばにアンプル剤から始まったといわれる。しかし何といっても1962年(37年)に大正製薬の「リポビタンD」の登場は画期的な出来事だった。ビタミン類にタウリンを配合した医薬品だが、ジュース感覚で飲めて、発売と同時に売れ出した。
日本は東京オリンピックを前に、高度成長が始まっていた。この年から1本足打法でホームランを量産し始めた王選手をコマーシャルに起用したのが当たった。プロ野球は川上が監督に就任した翌年で、長嶋、王のONコンビが活躍する巨人全盛時代に入ろうとしていた。
この年から1965年(昭和40年)までの間に、相次いで製薬メーカーのドリンク剤が売り出される。発売当時の「リポビタンD」の価格は150円だったが、1963年(昭和38年)に100円に引き下げられた。理由は分からないが、前年(昭和37年)に大塚製薬の「オロナミンC」が発売されたことと無縁ではないかもしれない。「オロナミンC」の価格は120円だったからだ。
これが初年度でいきなり1700万本も売れた。単純計算すれば20億円を超える売り上げになる。さらに翌年には3300万本になる。ところが医薬品のドリンク剤はすべてで12億円、トップの「リポビタンD」はその6割ほどだった。突如登場した食品系の栄養ドリンクは医薬品系のドリンクをアッという間に追い抜いた。
「そもそも医薬品のドリンク剤にならなかったから、栄養ドリンクで発売したといわれている」と加藤さんはいう。理由は「オロナミンC」には炭酸が使われていたことだ。確かに飲むとシュワーとくる炭酸が爽快感を与える。同じ年に米国から「コカ・コーラ」が上陸して、「スカッと爽やかコカ・コーラ」でブームとなっていた。これも影響したかもしれないが、いくら爽快でも医薬品のドリンク剤の規定に炭酸はなかった。それで「オロナミンC」は医薬品にはならなかったのだという。
面白いもので、炭酸入りが医薬品のドリンク剤に認められていれば、今の「オロナミンC」はなかったかもしれない。医薬品でないため、薬局では扱ってもらえなかった。しかしこれが幸いした。スーパーマーケットなどの食品を扱う店が扱ってくれたことで、医薬品より大きな市場で売られることになった。これが爆発的な売り上げにつながっていったのだ。
このオロナミンという名称は大塚製薬がそれ以前に出していた「オロナミン軟膏」から取ったものらしい。小学生の私は「頓馬天狗」というテレビ番組に夢中になったが、この主演で、「オロナミン軟膏」の宣伝にも起用されていたのが、俳優の大村崑だった。
大塚製薬は「オロナミンC」でもこの大村崑が起用した。テレビCMだけでなく、メガネがずり落ちそうな大村崑の写真のホーローの看板が全国の食料品店などの壁を飾った。
「今でも田舎に行くと、時たま見かけるやつだよ」という。そういえば歌手の水原弘や女優の由美かおるの殺虫剤や蚊取り線香の看板と並んで、この看板が張られているのをよく見たかけた。
「ところがそこに、“元気はつらつ”と書いてあった」
これが効能に当たる可能性があるのだそうだ。ボトルは茶色のガラス瓶で、ドリンク剤と変わらない。「このまま捨て置くわけにはいかない」と厚生省(現厚労省)が考えたからといって不思議はない。
(ヘルスライフビジネス2018年3月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)