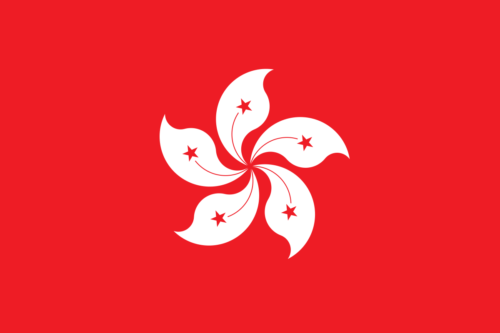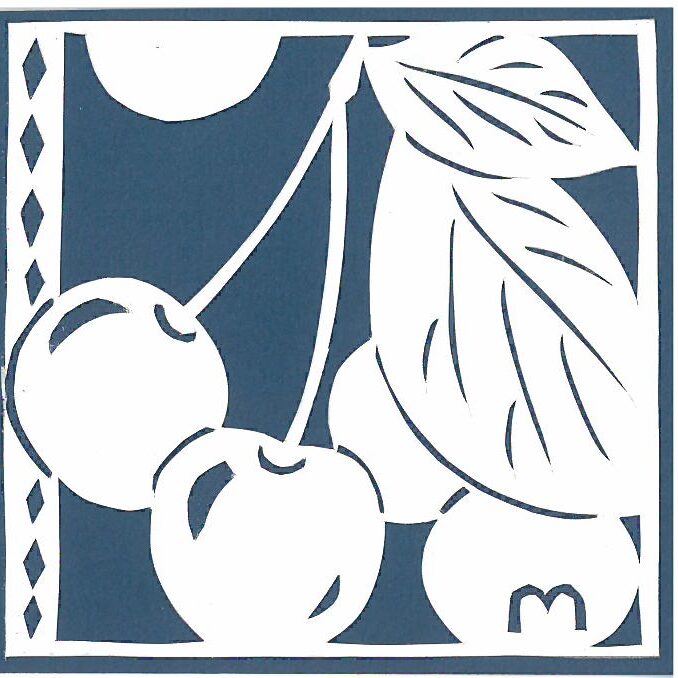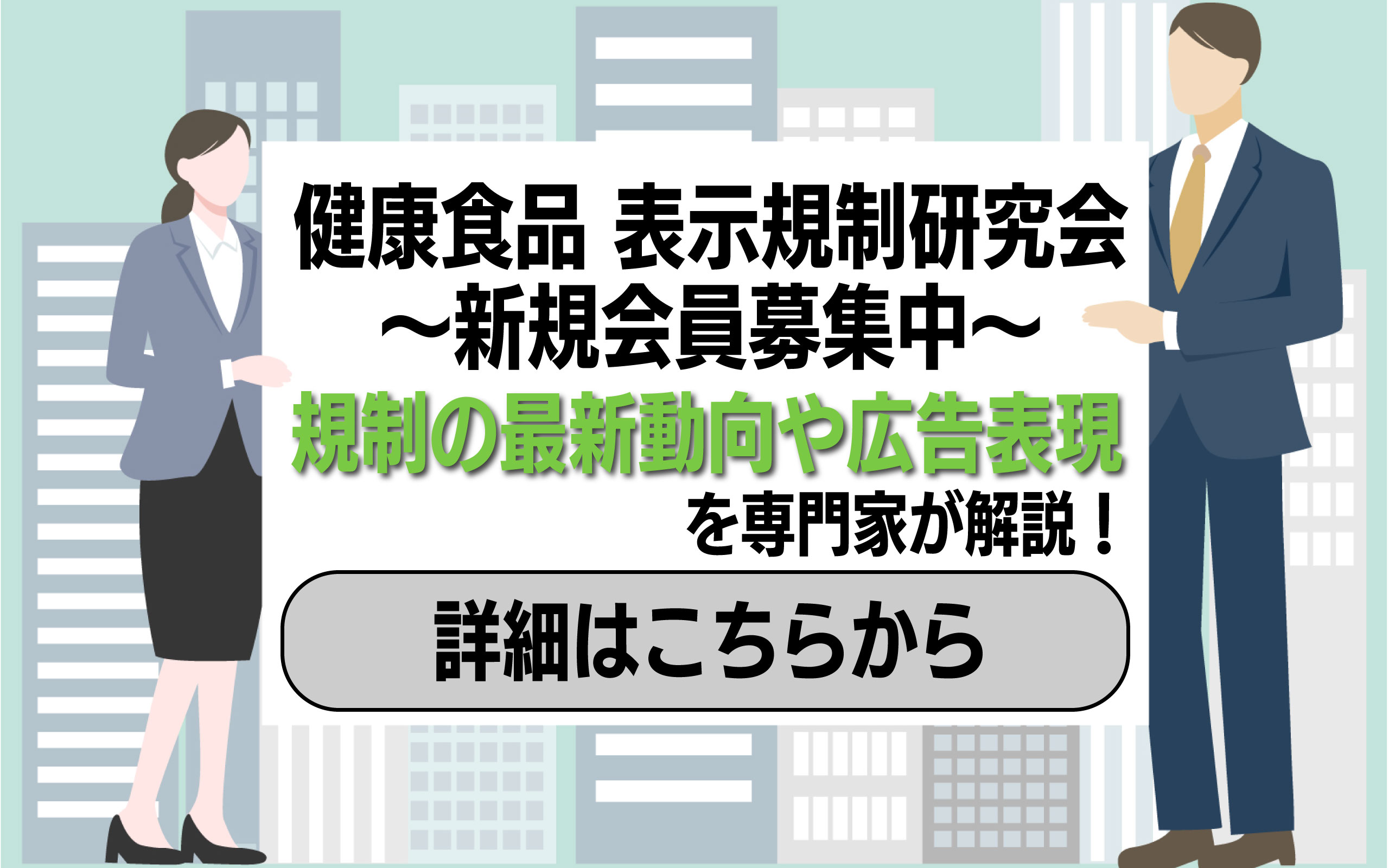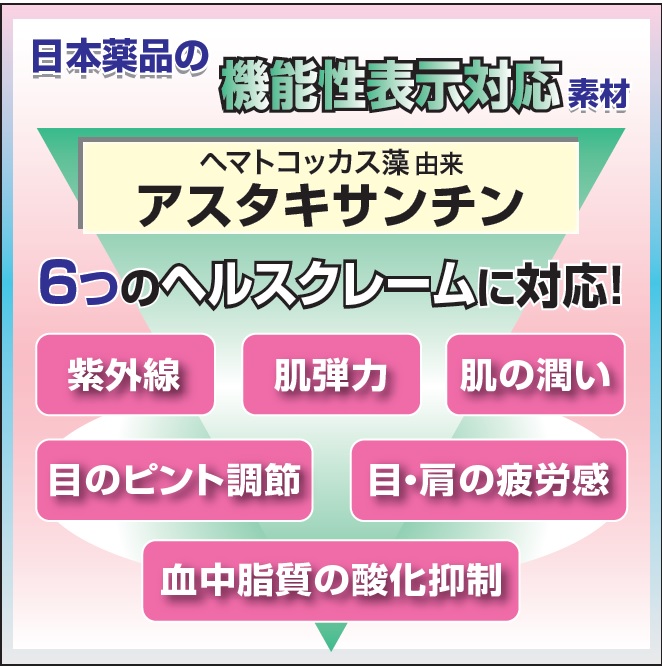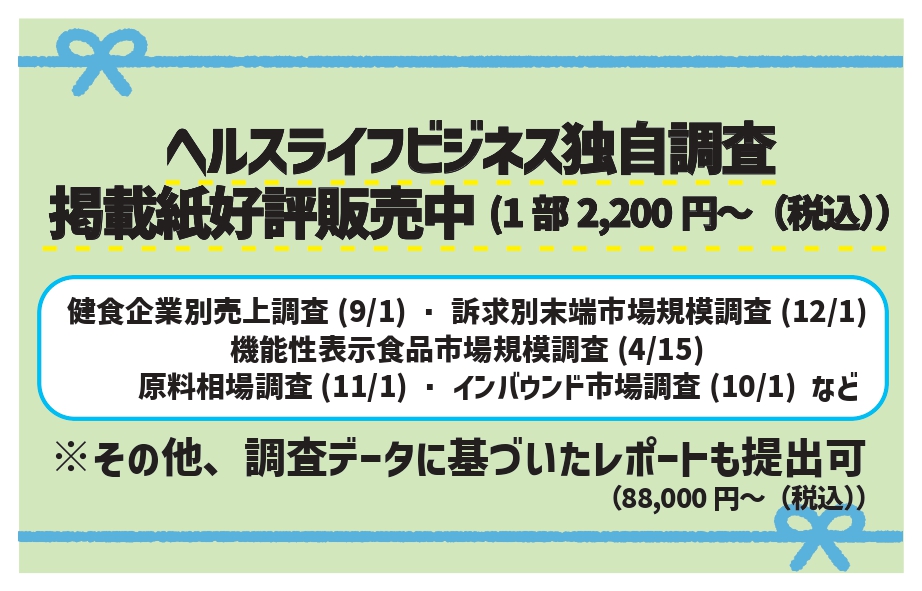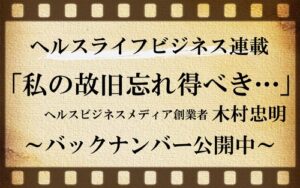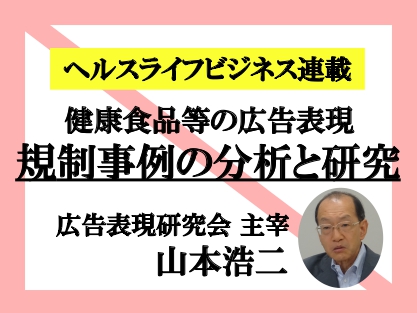食品と医薬品の接近で境が曖昧な時代へ(95)
バックナンバーはこちら
「もう一つがローヤルゼリーだ」
1961年(昭和36年)の薬事法大改正の施行と1971年(昭和46年)の「46通知」の間の10年間に医薬品と食品を巡って、大きな変化が起きていた。ドリンク剤のように食品と見まがうような医薬品が登場する一方、栄養ドリンクのような医薬品のような食品も現れて、食品と薬の境目が分からなりつつあった。時を同じくして、もう一つ、健康食品といわれる新しい食品が出回るようになった。その代表がローヤルゼリーだった。
2400年前に古代ギリシアのアリストテレスが出筆したといわれる「動物誌」の中にそれらしき記述があるそうだ。しかし今から200年前にスイスのミツバチ研究者のフランソワ・ユベールという人が自身の著作「蜜蜂の新観察」の中で、「ゼレー・ロワイヤル」と書いたのが世の中に登場した初めだといわれる。
これが広く知られるきっかけになったのは、1954年(昭和29年)のことだ。すでにフランスでは保健省認可の医薬品になっていた。これが80歳を超えて肺炎で死の淵にいたローマ法王ピオ12世を救った。奇跡的に回復した法王はその後に、世界養蜂会議で「ローヤルゼリーのおかげで命が救われた」と話した。このニュースは世界を駆け巡った。
日本では1957年(昭和32年)に名古屋の井上丹治という養蜂家が、人口王台でローヤルゼリーの量産法を開発し、1960年(昭和35年)には生産が始まった。欧州で医薬品だったためか、日本でも最初から医薬品とて扱われていた。すでに1963年には岐阜のハチミツの企業の秋田屋が生ローヤルゼリーで初めて医薬品の製造承認を得たという。これ以降、ドリンク剤やカプセルの形態の医薬品が出回るようになる。同じ頃に健康食品としてのローヤルゼリーも売られるようになっていた。
「医薬品だが、食品としても使える。この辺りが事をややこしくさせている」と加藤さん。
この健康食品のローヤルゼリーを誰が始めたかは定かではない。加藤さんの記憶では「森川磐石さんのところが最初じゃないかなァ」と言う。
今もこの会社はあるが、創立は1967年(昭和42年)だが、創業はさらにさかのぼる。とにかく創業者の森川磐石という人はローヤルゼリーの健康食品の草分けの一人らしい。量産法開発から10年たっていたが、この頃にはいくつもの会社から製品が出ていたようだ。最初は採取したままが良いとされ、そのまま“生ローヤルゼリー”として売られていた。しかし常温のままの生では変質するといわれようになった。それで白砂糖で包んで糖衣錠にしたものが売られるようになった。1969年(昭和44年)には同じ熊本の森川ローヤルゼリーという会社からハードカプセルの製品も出ている。
糖衣錠もハードカプセルも医薬品に使われている形状だった。使われている成分や素材が同じな上に、形状までもが同じというわけだ。これは栄養ドリンクとも似ている。
「ということは医薬品とどこが違うのかという思う人が出て来るのも自然だ」と加藤さんは言う。確かに、そういわれると「なるほど」と思う。
さらにこの年にはジャパンローヤルゼリーが会社を設立して訪問販売を始めている。つまりこの頃にはローヤルゼリーのブームが始まっていたのだ。
「そうなると、どうしたって効果を言って売りたくなる人が出て来る」
それも無理もない話だ。何といったって、フランスでは医薬品だ。ローマ法王を死の淵から救った。さらに日本でも医薬品にもなっている。岐阜薬科大学で有効成分の研究も始まっている。さらにカナダではがんへの効果の研究が行われている。日本でも渡会浩、竹内孝雄などの医師たちが臨床に使い始めて、この報告がマスコミをにぎわすようになった。
この頃、大手新聞に載った広告を見ると、「夏の疲労回復にローヤルゼリー」、「より強く、より美しく、より健やかに」といったキャッチコピーが使われている。
「食品の方からするとそうでもないが、医薬品の側からみる捨て置けないというのも頷ける」なぜならば、疲労回復は医薬品のドリンク剤の効能なのだ。
(ヘルスライフビジネス2018年3月15日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)