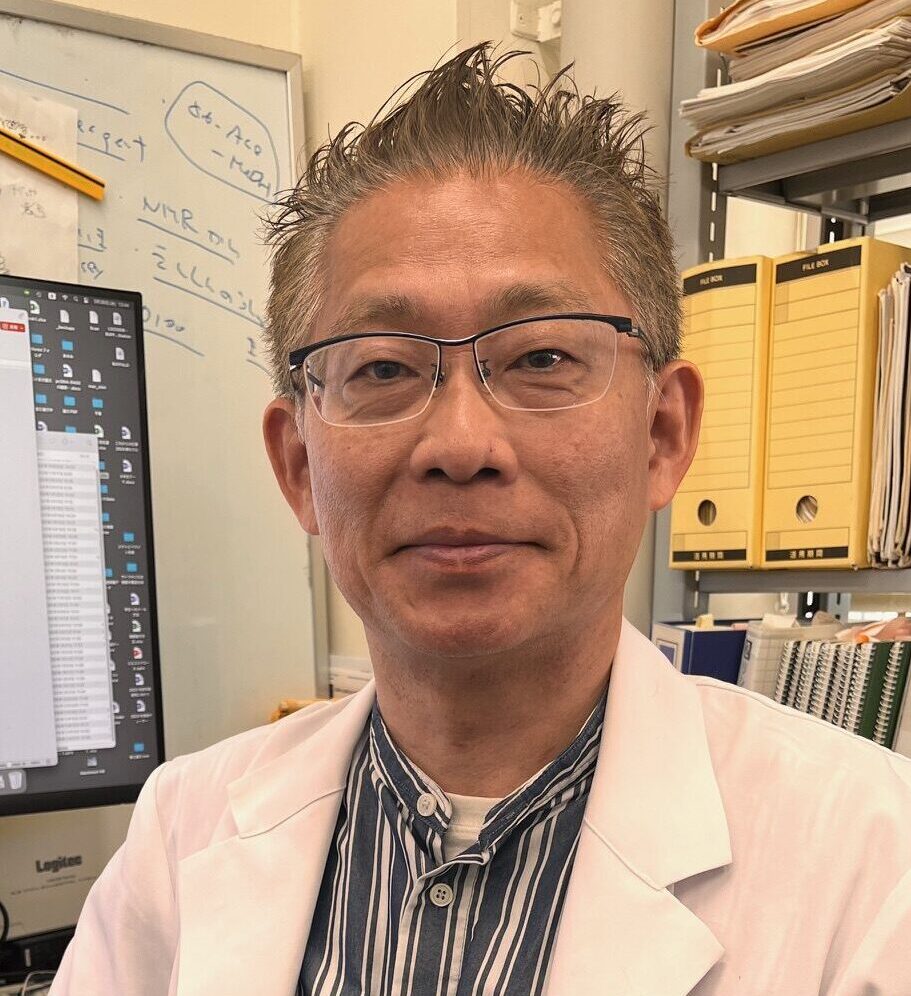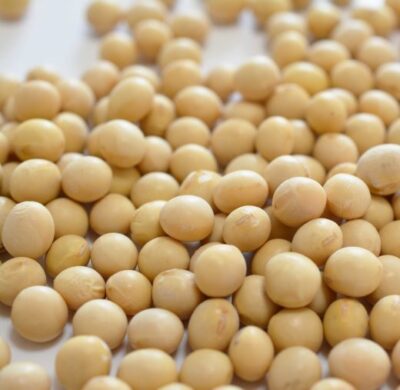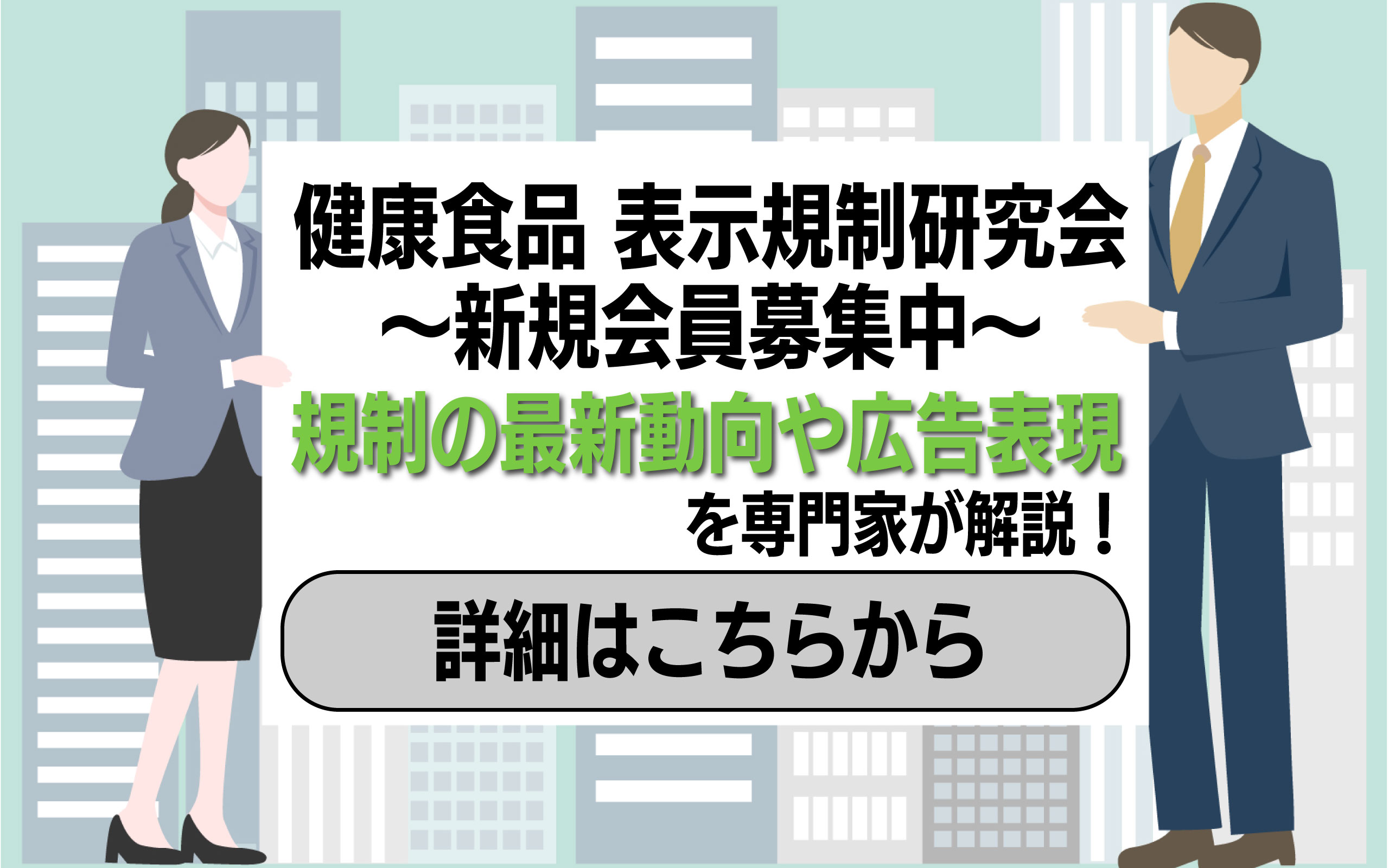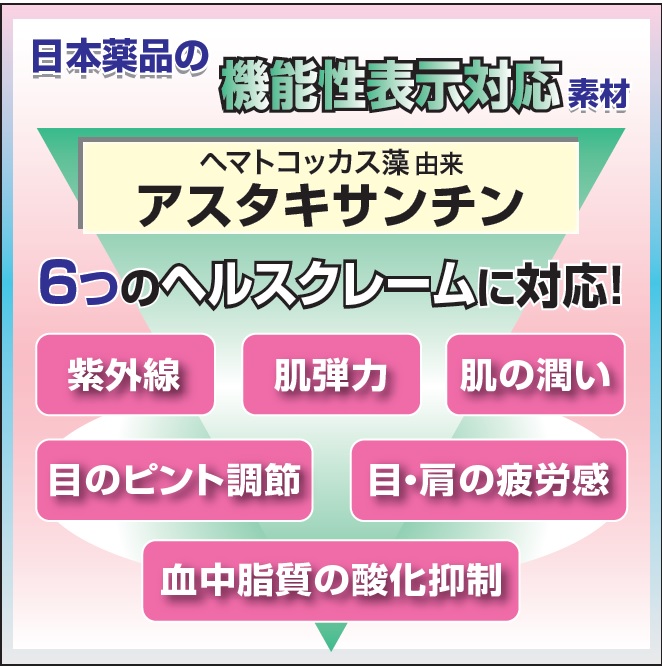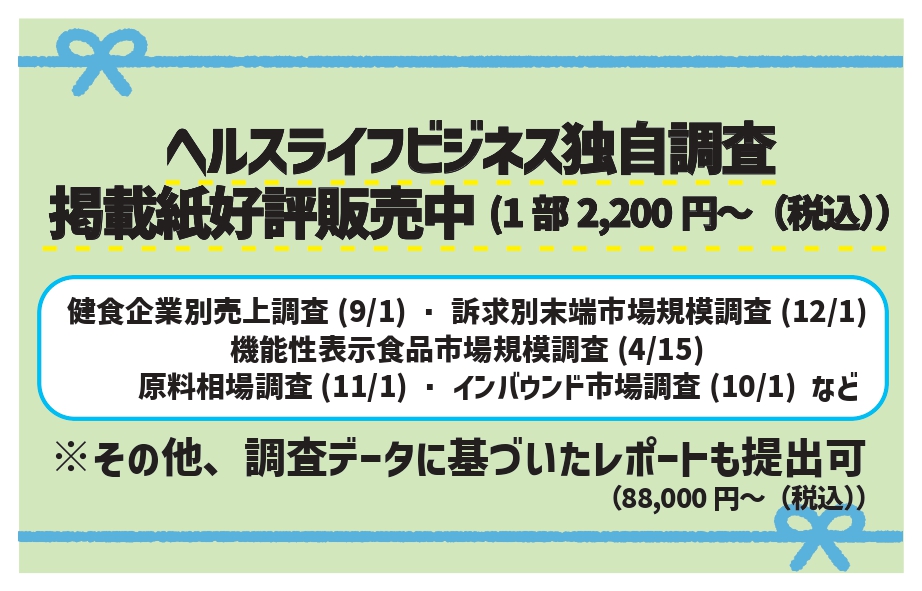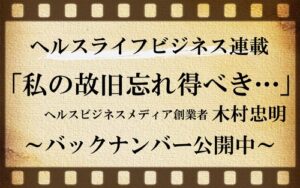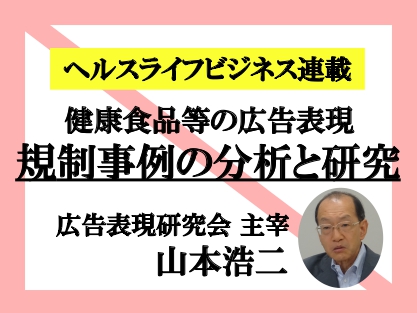今こそ、個の栄養学への転換が必要(126)
バックナンバーはこちら
日本人はどんな栄養状態にあるかを調べた国民栄養調査が毎年春になると発表され、新聞紙面を賑わしている。それによると、日本人の栄養摂取は「脂肪の摂取がやや多い」、「カルシウムが不足ぎみ」、「一部の女性に鉄欠乏による貧血が心配」、「塩分を減らす必要あり」といった見出しが紙面で踊っている。こうした記事が載る度に、日本人の栄養摂取に問題はないというと、誰もがそう思うようになる。恐らく書いている新聞記者自身がそう思っているに違いない。
「問題は平均値の人だけが足りているに過ぎないんだよ」と渡辺先生は言う。言われてみると、なるほどと思う。確かにテストの平均点が60点だとしても、それ以上のやつもいれば、それ以下のやつもいる。皆が60点というわけではない。
と言うと、渡辺先生はニコニコしながら「そういうことだ」と言う。ところが岩澤君の方を見ると、どうもよくわかっていないようだ。
そこで「例えば…」といって、岩澤君に説明した。貴方や葛西博士は昼飯のご飯を2杯は食べるだろうというと、朝食も夕食もだいたい2杯食べるという。岩澤君は体育会系だから分かるが、葛西博士は運動もしないのにどうしたことか大食いった。なのに太るのを気にする。それでたまにダイエットをする。昼飯抜きと階段を1段置きに駆け上がる。しかし大概続かない。
彼がダイエットを始めると、我々はスナック菓子の食べかけを机にそれとなく置いておく。それを見つけた彼は欲望に負けて、持ち主への断りなしに手を伸ばす。そしてバリバリとすべて食べてしまう。これを我々の間では「葛西ホイホイ」と呼んでいた。当時アース製薬のゴキブリ駆除器がテレビ宣伝で有名になっていたが、それになぞらえて編集長が命名したのだ。
「木村さんはどのくらい食べますか」と岩澤君が聞く。
私は朝食をほとんど食べなかった。理由は朝寝坊だ。食べるくらいならぎりぎりまで寝ていた方がましだと思っていた。昼は食べるが、夜は酒を飲むので食べない。アトキンスダイエットというのがあったが、そんなつもりはなくても自然と糖質制限食になっていた。
それにしても2人が1日に食べるご飯の量は私には信じられない量だ。朝、昼、晩で茶碗に6杯になる。
しかし、普通の人の食事量は1食当たり茶碗1杯と言われていた。
「つまりさまざまな人はいるが、日本人のご飯の平均値は一日3杯だというわけだ」。そう言うと、岩澤君はようやく合点したようだ。栄養も同じで平均値でいくら栄養が足りているからといって、すべての日本人が栄養所要量を満たすだけの栄養素を摂っているわけでないことは明らかだ。
「だから集団を対象にした栄養学ではダメなんだ」と渡辺先生はいう。栄養学は軍隊と共に発達してきた学問だ。兵隊という集団が戦争という限られた条件のもと、身体の健康を維持するために不足を起こさない最低限度の栄養の必要量を定めたものが栄養所要量だ。米国の軍で使っていた基準を1940年代に一般用に改めたのが「RDAs(栄養所要量)」だ。これは特定の集団の最大公約数に当てはめた基準なのである。だから日本でもこれを採用して以来、学校の給食などに使ってきた。
「これでも一時的なら良いが、ずーとこれだと問題が起きる」
基準より少ない人や多い人は同じ状態がずっと続くので、栄養障害が起きてきてしまう。それが生活習慣病の一因になっているというわけだ。
「今こそ個の栄養学への転換が必要な時代なんだ」
(ヘルスライフビジネス2019年7月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)