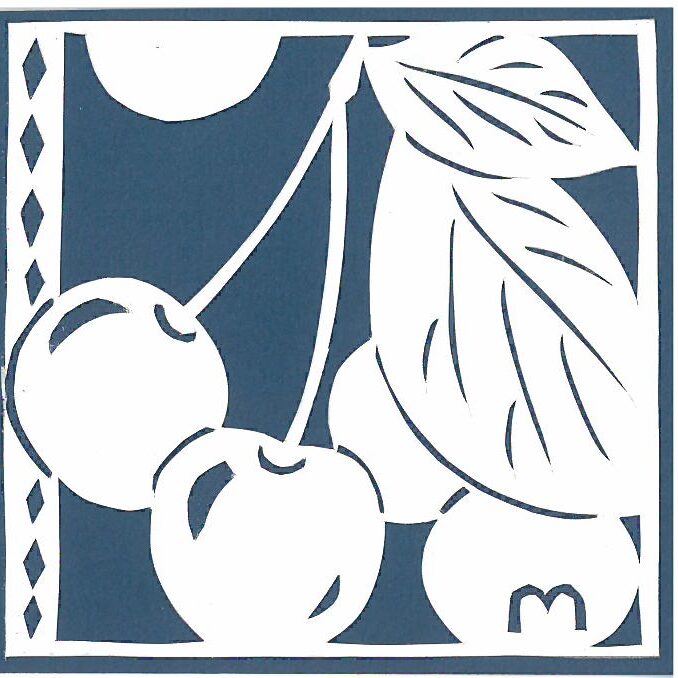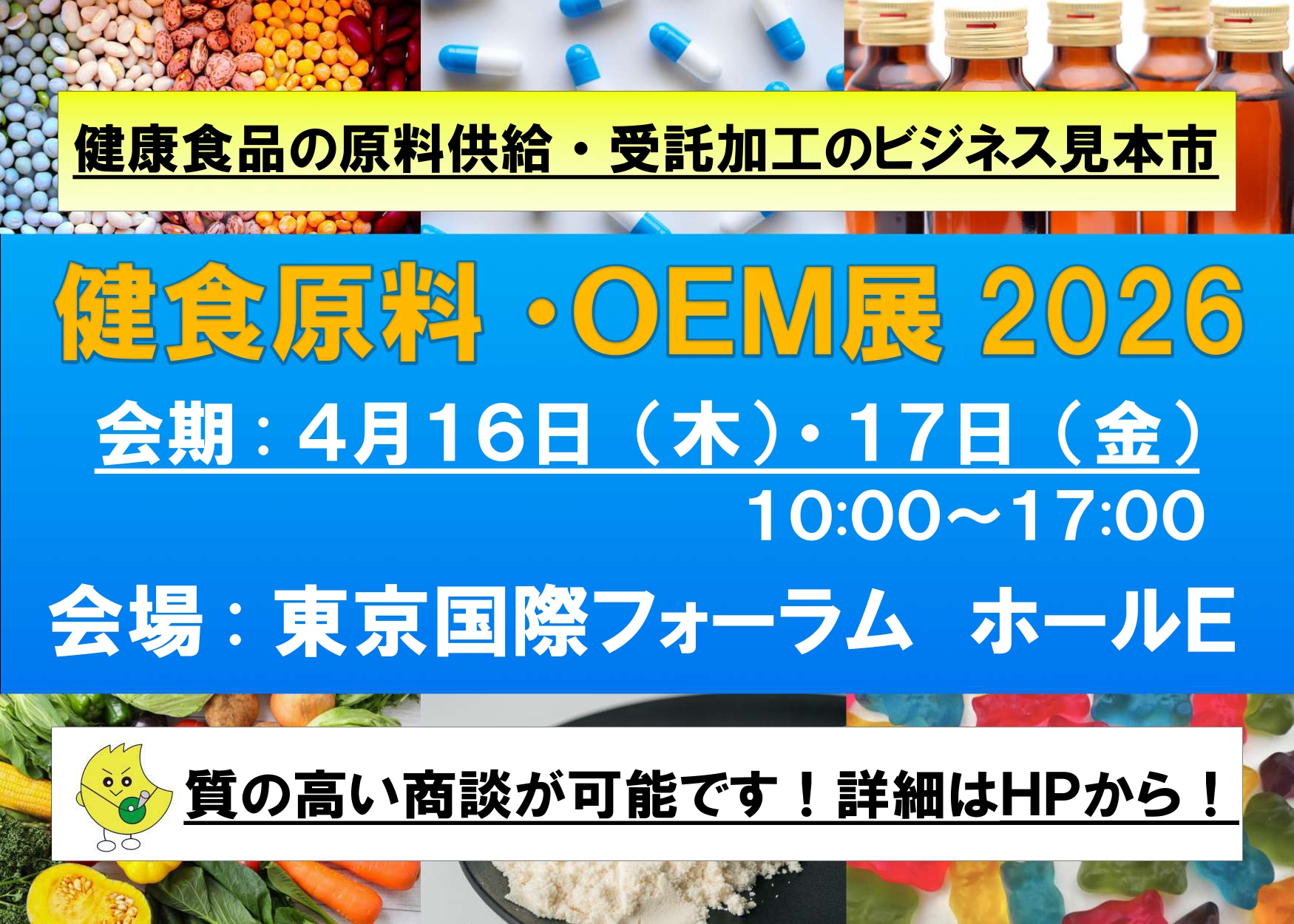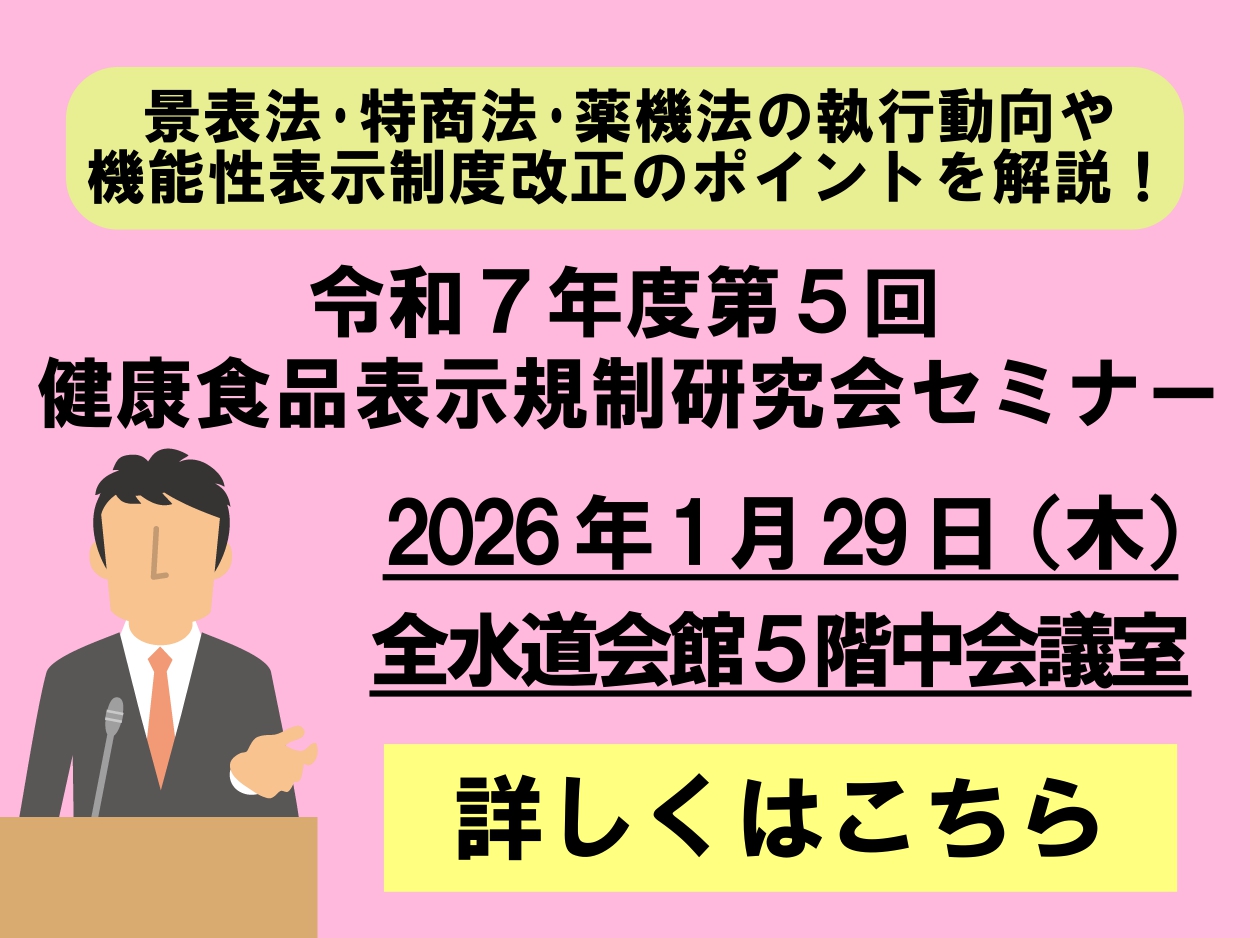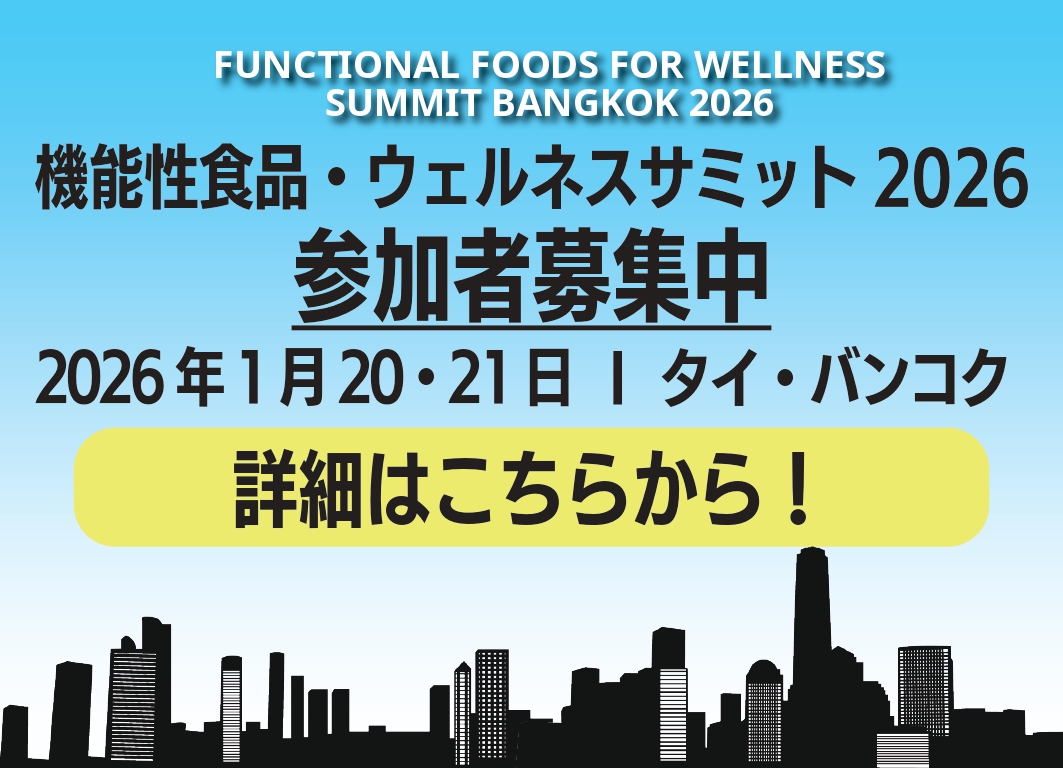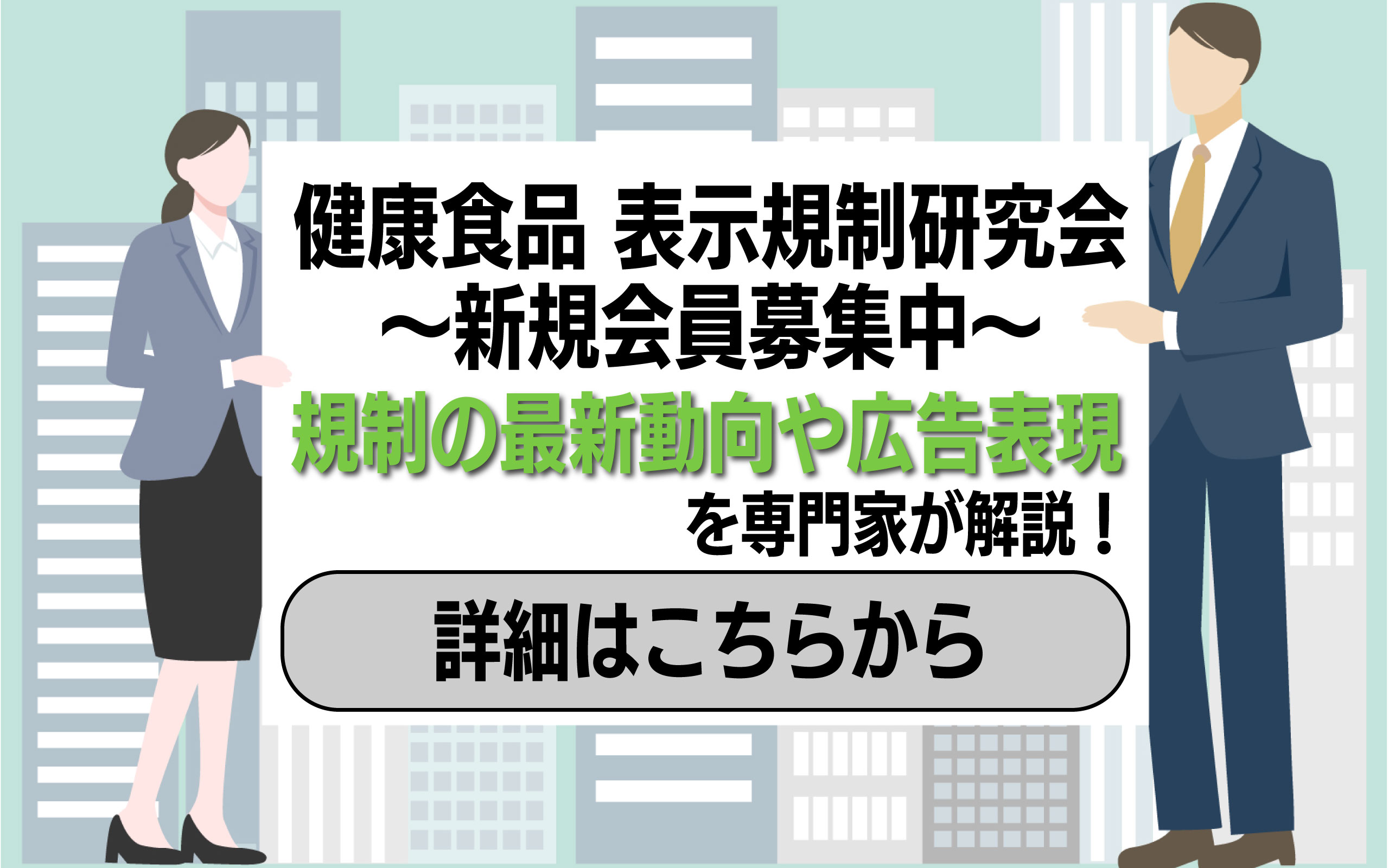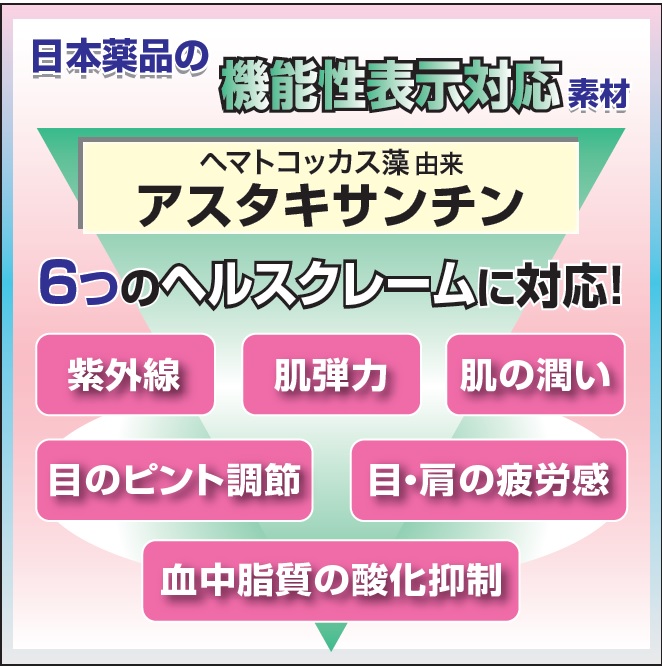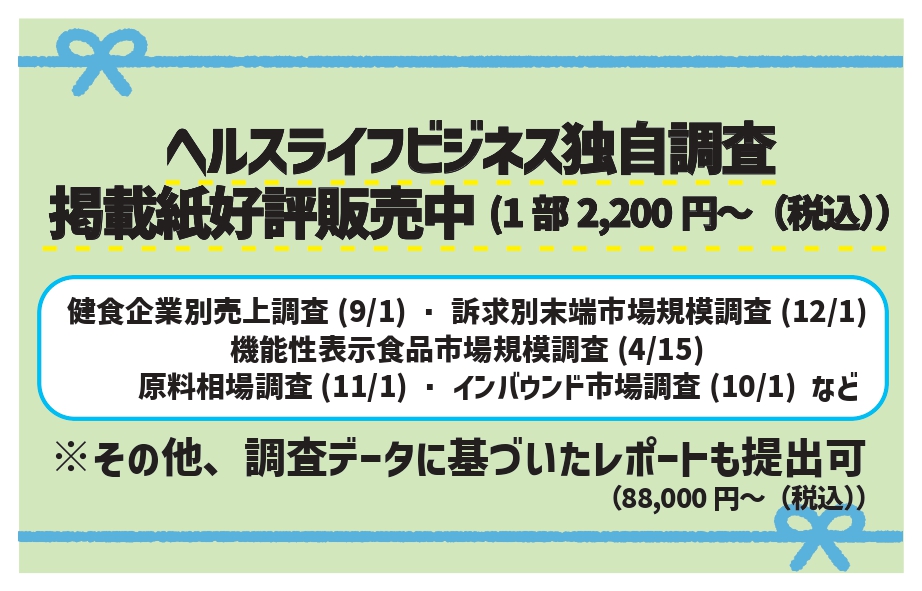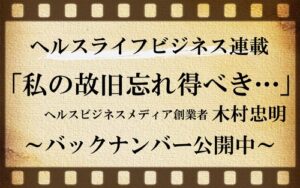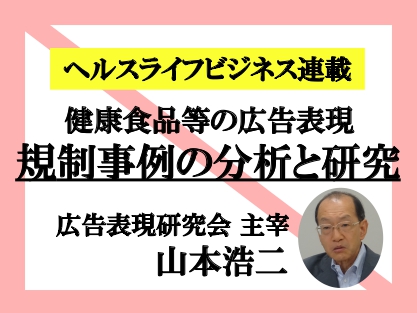- トップ
- ニュース , ビジネス , ヘルスライフビジネス , 健康・美容製品
- 【解説】災害時の食問題と健康…
【解説】災害時の食問題と健康食品の可能性
炭水化物への偏りが重要な課題に
災害大国といわれる日本。南海トラフ地震に関する注意報が政府から発表され、人々の災害時に備えた備蓄への意識も一層高まっている。災害の現場では環境の変化、支援物資の偏りによる栄養不足など食事に関する課題が多く、感染症や疾患につながるリスクが高まる。こうした栄養問題の対策としてサプリメントが利用されている。災害現場の食や栄養の問題と、健康食品の役割を考える。(編集部:村田美唯花)
エコノミークラス症候群のリスク高まる
災害発生後の避難所生活では、通常時とは異なる健康リスクに備える必要がある。慣れない環境によるストレス・疲労、食欲減退・不眠などの症状が多くみられ、さらには避難所などでの密集した生活が続くことで感染症や食中毒のリスクも高まるとされる。さらに、身体活動量や水分・食事の摂取量が平時よりも減少することで、血液循環が悪化しエコノミークラス症候群のリスクが高まり、死に直結するリスクも生じるという。さらには栄養の偏りによる血圧や血糖値の上昇、下痢や便秘などの症状が多く見られる。ビタミンB2が不足すると口内炎が現れるため、避難所での栄養不足のサインとなる。さらに避難生活が長期化すると、肥満や心臓血管疾患や脳血管疾患など血管系の病気も増加し、最終的には災害関連死に繋がる可能性がある。
東日本大震災で日本栄養会災害対策本部が宮城県気仙沼市で実施した被災地の栄養問題の調査結果の報告には、「支援物資(食材)の偏り:炭水化物を中心とした支援物資(おにぎり、菓子パン、カップ麺など)による高炭水化物、高塩分食が続き、2か月以上が過ぎても野菜の配送が充足されていない避難所が多かった」と記されている。
災害時の栄養支援でサプリの使用量が1位
内閣府が令和4年に発表した「防災に関する世論調査」の概要では、自然災害への対処法で家族や身近な人と話し合う内容として重要なことといして64・7%の人が「食料・飲料水について」と回答。災害時の食料確保に対する意識の高さが明らかとなった。
現在、災害時向けの備蓄食の販売に特化した企業は限られるが、防災意識が高まるにつれ通信販売などを中心に災害食事業に参入、新商品の発売をする企業も少しずつ増えている。ロート製薬(大阪市)は今年1月、5年常温保存可能な循環備蓄おにぎり「ハートフード」を発売。フェリシモ(神戸市)は、ケンミン食品のビーフン、ネスレ日本の「ミロ」、山垣畜産のレトルトタイプのビーフシチューなど10種類の食品をセットにした「備蓄でお守りKOBE BOX2」を発売。長期保存にこだわらず、次の半年の無事を願って備蓄する循環型の「ローリングストック」を推奨している。ライフラインが制限されるなかで普段の食事と変わらない美味しい食事の再現を目指した企業の取り組みが目立つ。また、自社HPなどで製品のPRともに備蓄の啓発を行うケースも多数みられる。
これまで備蓄食として出されている商品は、エネルギーの補給を目的としており、栄養素の補給を目的としたサプリメント剤形の災害は市場には数少ない。
国民生活センターが実施した「災害に備えた食品の備蓄に関する実態調査」では、栄養補助食品16・2%、サプリメント・健康食品は11・6%であることがわかった。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 産官学連携研究センター 災害栄養情報研究室・室長の坪山(笠岡)宜代氏は、「災害時の栄養支援で一番使用量が多かった食品はサプリメントでした。炭水化物に偏った栄養バランスを整えるため、主にマルチビタミンなどが活用されています。日本災害食学会でも、マルチビタミンや魚のアミノ酸のサプリメントを災害食として認証しています」と話す。
「サバイバルフーズ」を展開する、セイエンタプライズ(東京都)は7年保存が可能な災害時用サプリメントを2021年より販売開始している。ビタミン類を従来のサプリメントより高含有で設計。同社の平井雅也社長は、「当社では、缶に入れた食事タイプの備蓄食を展開してきましたが、それだけでは補えない栄養素を補給する目的でサプリメントを開発しました。自治体や病院からも引き合いが増えています」とコメントしている。
専門家「おかずを中心とした製品設計を」
坪山氏は「2011年に厚労省が発出した災害時の栄養基準(参照量)を検討する際に参加し、災害時に摂ってほしい栄養素としてエネルギー・たんぱく質に加え、水溶性ビタミンのB1・B2・Cの5つに参照量を設けました。水溶性ビタミンは体内のストックが少ないため、欠乏症が早く出ます。中でもビタミンB群は、炭水化物を分解する際の補酵素として働きます。炭水化物をエネルギーに変えるにはビタミンBが必須です。ビタミンCは、ストレスの多い過酷な状況下では必要不可欠です。しかし、厳選した5つの栄養素でさえ補えていないのが現状です。まずは、これらの栄養素を補えるような『おかず』を中心とした製品設計を呼びかけています。
日本災害食学会の定める認証制度では災害食に求める基準として、常温で保存ができる・調理の手間があまりかからない・そして第一に安全であることなどを定めています」としている。
↓↓ヘルスライフビジネスの購読(電子版・紙版)のお申込みは以下よりお願いします↓↓