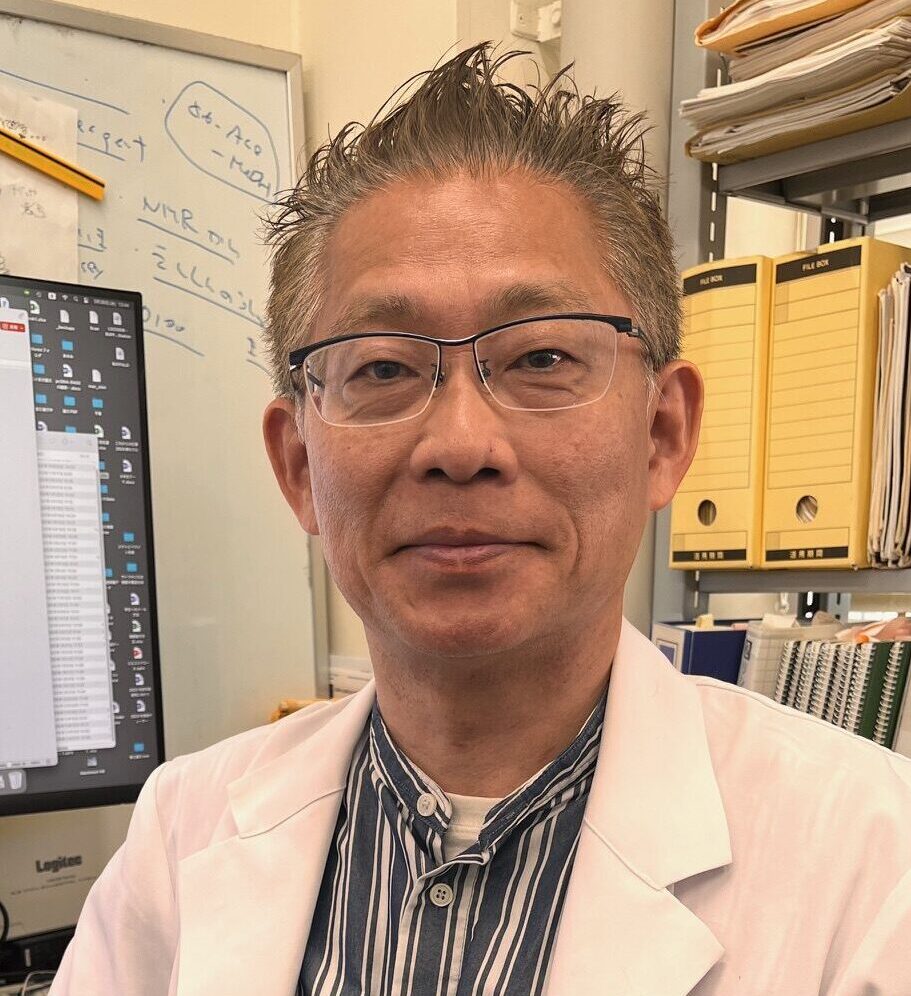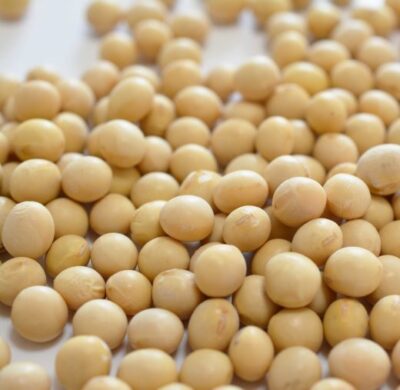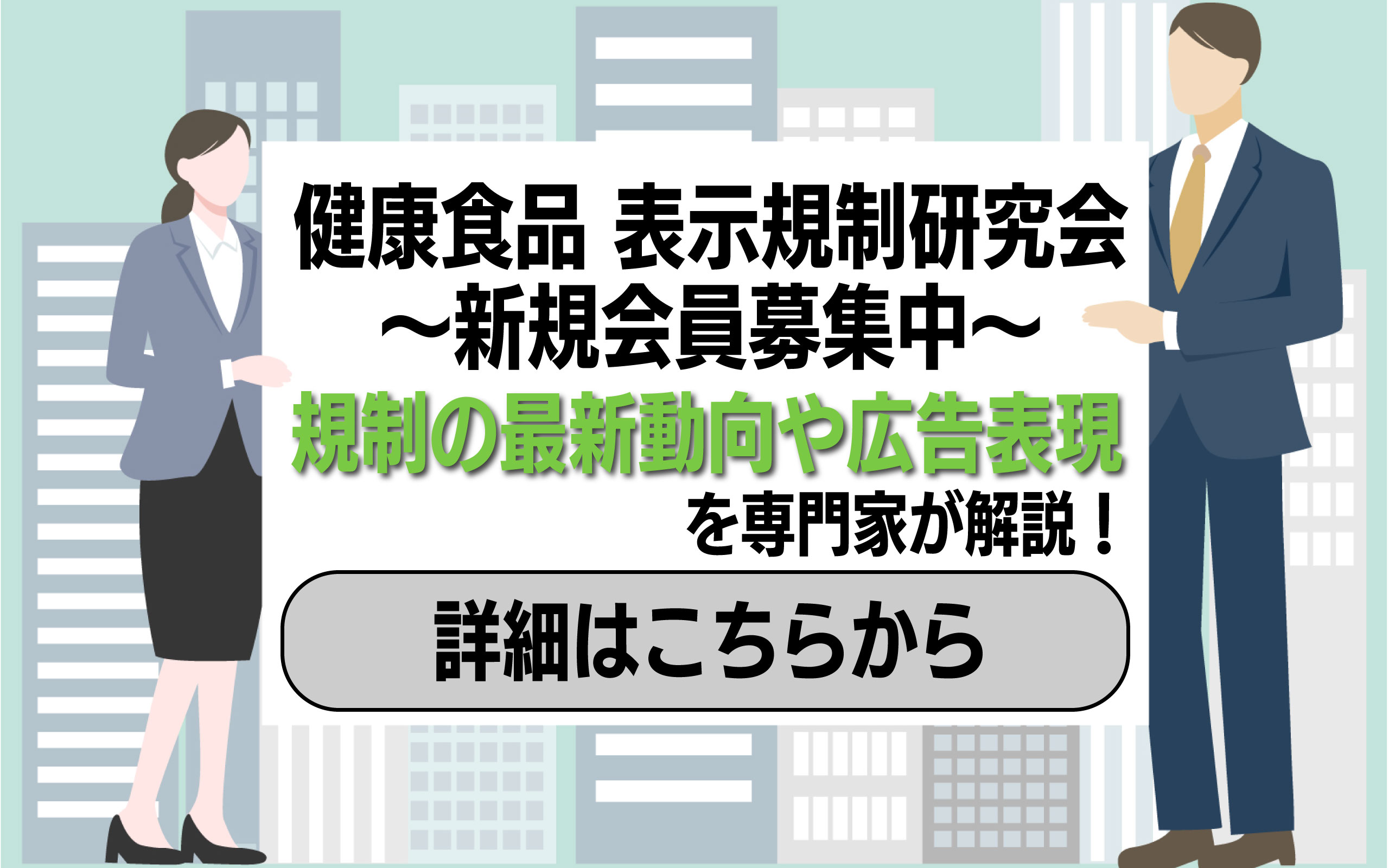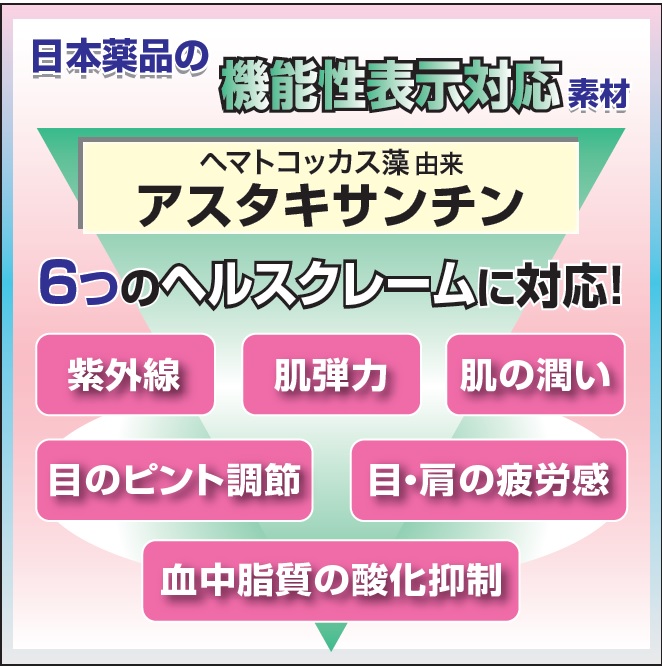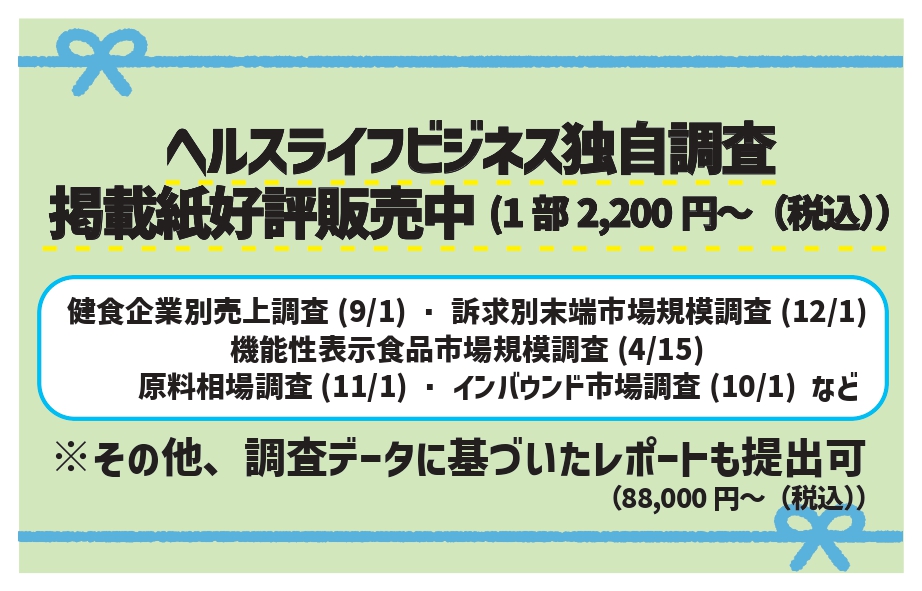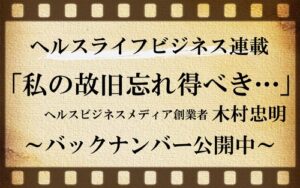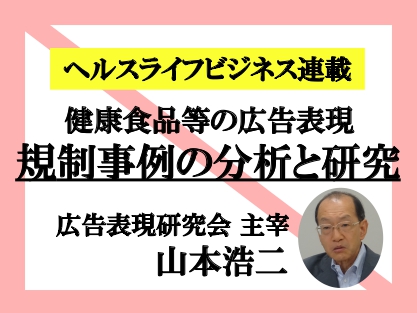- トップ
- ビジネス , ヘルスライフビジネス
- まさか経企庁が乗り出して来よ…
まさか経企庁が乗り出して来ようとは(137)
バックナンバーはこちら
年明けから雪の日が多く、例年より寒い日が続いていた。いつもなら3月の20日前後のはずの桜の開花宣言が、だいぶずれこんでいた。そんな3月末に健康食品の業界にとって嫌なニュースが流れた。経済企画庁が健康食品の実態調査の結果を発表したのだ。
この頃、役所の健康食品についての発表は取り締まりと相場は決まっていた。調査の類は取り締まるための理由付けといったところだ。というのも厚生省は薬の部局も、食品の部局も健康食品を認めていないのだから、当然といえば当然である。
この時も案の定、内容は否定的なものだった。調査は300もの商品のパッケージやラベルを対象にしているが、それだけでなく商品の販売に使うチラシやリーフレットにも及んでいた。
このためか、違法な表示が続々と出てきた。特に、調査対象となった商品の半分以上に使用量が書いてあった。使用料は薬事法上の解釈では用法用量とされ、医薬品以外に書いてはいけないことになっていた。
さすがに効果についての記載は商品のパッケージやラベルにはほとんどなかった。
しかし、チラシやリーフレットには直接的に効果を表示していないないが、暗示するような表現をしたものがかなり見つかった。さらに情報提供を求めたところ、疾病の予防や治療に効果があるような資料を送りつけてくることも多かったという。
「役所の中によほど業者の事情に明るい者がいるに違いない」
編集長は経企庁の通知のコピーを見ながらため息をついた。緊急の編集会議の席である。
「それにしてもなんで商品に効果が書いてないんでしょうか」とまだ駆け出しの岩沢君が聞いた。
すると規制に詳しい葛西博士が、「それは当然だよ」といいながら、その訳を語り始めた。効果を謳えば薬事法違反になる。この頃にはたいていの業者はそのことを知るようになっていた。
このとき商品のパッケージやラベルに表示してあると、商品を回収しなければならなくなる。これは商売には痛手だ。取引先にも迷惑をかける。こうしたリスクを避けるため、この頃には多くの業者が商品のパッケージやラベルに効果を表示することはなくなっていた。
しかしチラシやリーフレットでは婉曲に効果を謳う。そうしないとまったく消費者に情報が伝わらないからだ。しかし見つかれば行政指導である。その場合は、素直に従い、「もうしませんと」との誓約書を書き、チラシは廃棄すればよいのである。
「敏い業者はそこに気が付いた」
葛西博士の話に熱が籠る。まるで無声映画の弁士である。
チラシを廃棄してもダメージが少ない。ただし同じことを繰り返すと、仏の顔も三度までである。改心していないとみなされれば、悪質という烙印を押されて警察に回される。
ただし役所が回して寄こしても、警察が起訴するかどうかは分からない。公判を維持で来るかどうかの判断のカギになるのだそうだ。
「それよりも商品は店頭で買ったとして、チラシやリーフレットはどうやって集めたんだろう」と編集長。
言われてみれば不思議な話だと誰もが思った。しかし葛西博士だけはそのことも知っていた。
(ヘルスライフビジネス2020年1月1日号「私の故旧忘れ得べき」本紙主幹・木村忠明)